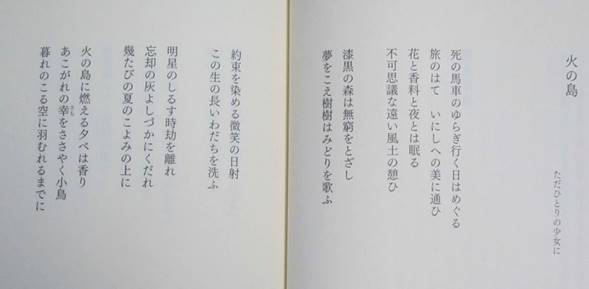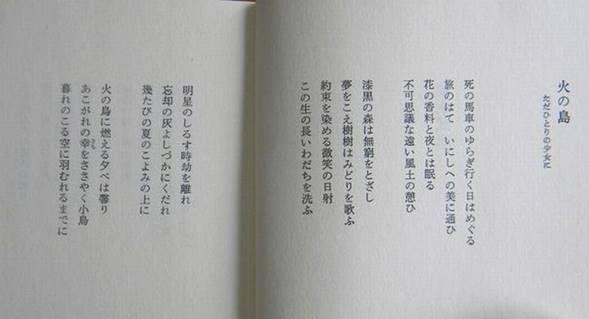HOME|入会案内|例会報告 |会誌紹介|電子全集紹介 | 関連情報 | 著訳書目録|著作データ | 参考文献|リンク集|玩草亭日和(ブログ)|掲示板(会員限定)
|
福永武彦研究会・例会報告(13)
第146回~第153回 (2014年5月~2015年9月)
|
 【第153回研究会例会】 2015年7月26日(日) 【第153回研究会例会】 2015年7月26日(日)
 【第152回研究会例会・平成27年度総会】 2015年5月31日(日) 【第152回研究会例会・平成27年度総会】 2015年5月31日(日)
 【第151回研究会例会】 2015年3月22日(日) 【第151回研究会例会】 2015年3月22日(日)
 【第150回研究会例会】 2015年1月25日(日) 【第150回研究会例会】 2015年1月25日(日)
 【第149回研究会例会】 2014年11月23日(日) 【第149回研究会例会】 2014年11月23日(日)
 【第148回研究会例会】 2014年9月21日(日) 【第148回研究会例会】 2014年9月21日(日)
 【第147回研究会例会】 2014年7月27日(日) 【第147回研究会例会】 2014年7月27日(日)
 【第146回研究会例会】 2014年5月25日(日) 【第146回研究会例会】 2014年5月25日(日)
*直近の研究会例会報告は、本サイトのTOPページに掲載されています。
 第153回例会 第153回例会
【日時】2015年7月26日(日) 13時~17時
【場所】川崎市市民プラザ 210、 参加:13名(初参加1名)
- 冒頭に、前回例会で討論した「影の部分」のドイツ語訳(2007)に関して、発行の経緯、訳者ツキエ カオリさんとフンボルト大学、そして森鷗外研究所についての簡単な紹介と解説がSiさんよりありました。
その後、第一随筆集『別れの歌』を討論しました。全体を検討することはできませんでしたが、Miさんより神西清関連の種々の資料が配付・回覧され、一般に馴染みの薄い神西に関して、その文学と人となりの大略の紹介・解説がなされました。
休憩を挟んで、11月企画「文学フリマ」へ向けての小冊子作製に関してKoさんより報告・提案があり、また、Maさんより秋に予定している「文学散歩」に関する相談・提案がありました。
以下、発言者自身による要旨・感想を掲載します。
【発言要旨・感想】順不同(敬称略)
①Kuさん:『別れの歌』について
- 「別れの歌」の筆頭に「堀さんの訃報は僕等をおどろかせ、悲しませた」という一文があります。僕は、そこに、福永の堀に対する強い思い入れを感じました。福永は、堀の作品を熟読し、いい部分を吸収してきたと思います。渡邊啓史さんが、「水中花」について、この作品を堀辰雄の『曠野』の影響下にあると以前発表されたことを思い出します。随筆集を取り上げるとき、作者がわざと嘘も交えた随筆を書くことがありますから、随筆に書いてあることを鵜呑みにすることは、極めて危険です。ただし、自分の仕事も犠牲にして『堀辰雄全集』の完成に福永が長い間携わってきたことは、事実です。このこと一つを考えても、随筆集には、特殊な価値があると思いました。
②Naさん:『別れの歌』
- 「別れの歌」は堀辰雄氏の訃報から始まり、追悼と回想を中心に書かれた随筆集です。「よく生きられた生涯は、たとえ短いものであっても、人々の追憶の中に再びその生涯を生きるだろうから。」(P.201) ここに物故者への真意を端的にみることができます。小説とは違い、著者の日常が描かれている点は、心和むところがあり面白く、読んでいると落ち着いた気分になっていきます。「日の終り」の後半部分、隣家の違反建築に関する文は無くてもいいと感じます。しかし、文学者とは言え生活者なのだと思えば、かえって著者に親近感が湧くこともあるでしょう。
③Maさん:随筆集『別れの歌』を読む
- 1.ドイツ語訳『影の部分』(2007)について
2007年にベルリン・フンボルト大学に併設の森鷗外研究所が発行された福永武彦の短編小説の翻訳作品について、Siさん(独文科卒)の報告。
このドイツ語訳作品が、2012年の『草の花』のドイツ語訳に先行する最初のドイツ語訳ではないか、との推定。本そのものは、かって渡邊啓史氏が(現地より?)入手されたものを意欲ある若い研究者に提供されたもの。
Siさんの報告は、A4両面1枚に要旨がまとめられ、発行の経緯、訳者による著者紹介、訳者の紹介、フンボルト大学設立以降の歴史にも触れ、併せて森鷗外研究所設立の経緯とその意義、かって東ベルリンに属した大学の周辺の環境まで、簡にして要を得ている。ドイツにおける日本学が、日本そのものについて学ぶのでなく、日本語によって書かれたドイツあるいは、日本から見たドイツを学ぶことを主眼とするところに問題があるという問題点の指摘など、レジュメ外の話も面白く、この地を踏んだ経験を踏まえてのかつて東ベルリンに属した大学の周辺の環境、ブランデンブルグ門や、連邦国会周辺の案内は臨場感あふれて楽しかった。
翻訳は、「かなり丁寧でお手本的」な翻訳とのことだ。次の会誌制作の準備に余念がない中でよく読みこんで、フレッシュな若人の探求が、新しい道を踏み出していることを慶ぶ。いずれ論考として再会できるのも遠くはあるまい。
2.神西清 人と作品
堀辰雄周辺の人々の話には決まって登場するのに、作品を探そうとするとその姿は行方知れずになる。神西清は、私にとって長い間そんな印象の人物だった。チェホフの翻訳者として、また伝説的文学者として頭の片隅にその名は刻まれながら、今まで作品を読む機会はなかったのである。
実は長い間神西清を愛読し資料も集めてきたというMiさんの、思い入れ深いレクチャーは,積年の蒐集による選りすぐりの資料とともに溢れるばかりで停まるところを知らず、聴く側も時間を忘れた。
『堀辰雄全集』(新潮社版)の編纂にあたった福永、中村たちとのやりとりの一端をのぞかせる直筆書翰、53歳で亡くなったその一周忌に刊行された福永が編んだ『神西清詩集』、三島由紀夫が熱烈な賛辞を寄せ解説を付す作品集『灰色の眼の女』をはじめ、幅広く目配りされた沢山の書籍、資料が配布資料のほかに回覧された。
「車で来たので一杯資料を持って来られた」とのことだが、話自体が、さながら「人と作品まるごと神西清」であり素晴らしかった。活字化しないのはもったいなさ過ぎる。もちろん作品集はすぐさま注文した。
3.随筆集『別れの歌』について
一冊の随筆集を討論のテーマにするのは難しい。そこで、冒頭から始まり、後記に「堀辰雄と室生犀星とに関して私の書いたものは、―略― 殆どがこの中にある。」と福永が書いている堀辰雄との関係を考えることにした。そこで参考とした2冊を紹介したい。
小山正孝著『詩人薄命』(潮流社2004.12)、トップが「回想の堀辰雄」で何編かのエッセイが纏められている。小山正孝は杉浦明平、立原道造に属目された詩人であり、中村真一郎とともに『山の樹』に参加している。終生の友となる山崎剛太郎とマチネ・ポエチックの会に出席もしていた。福永との会話もすこしだがあった。『詩人薄命』には立原道造や野村秀夫など「四季」の詩人たちとの関係も生き生きと描かれている。堀辰雄が『四季』に対して持っていた熱情は相当のものだった、と小山は書く。『四季』をめぐる人々の姿が、戦争をとおした軽井沢や東京、盛岡や弘前の地にも及んで、小山正孝の敏感でややシニックな感受性でいきいきと再現される。小山氏の『別れの歌』ともいえる内容である。
もう一冊、私には馴染み深い中村真一郎著『戦後文学の回想』(筑摩書房、1963)をあわせ読んで、同時代の若き詩人、文学者たちの群像が3Dのように立ち上がる。そんな感じを私は持った。堀と福永の関係に停まらず、戦中戦後の時代、堀を中心に軽井沢集まり出会った詩人、文学者たち、そしてそこには、レクチャーを聴いて少しだが作品を読み、血の通った「神西さん」もいて、彼が身を挺して尽くした親友、魅力的な人柄が偲ばれる堀辰雄の姿があり、登場したそれぞれいずれ劣らぬ人間的な個性がひしめきしゃべりあっている。その魅力的な世界の端っこで、彼らの声を聞いているような気さえしたのである。
④Miさん:我が神西清
- 『別れの歌』(新潮社 1969)は、福永が日常親しんだ文人たちへの追懐と、自らの来し方への回想が、インティメートな文体で綴られる随筆集です。追分を舞台とし、一見ノンシャランな日常が記された短文にも、巻末の隣家との違反建築騒動の顛末にも、死の影が揺曳しています。「時間が主役を演じるように全体を按排し」た(後記)本文と、中川一政の挿画とが相俟って、堅固なひとつの世界を構成している作品集です。
その中から、今回は先輩文人の中でも知られるところの少ない、神西清(1903-1957)の人と文学に関して、多くの時間を割いて紹介・解説をしました。
私が神西清とその文学に惹き付けられて25年ほどになりますが、研究会の皆さんに紹介したことはありません。今回、丁度よい機会ですので、特に堀辰雄への神西の献身を、その全集編集者としての姿を通して見てみました。
Ⅰ.福永武彦が『新潮日本文学小辞典』(1968)のために執筆した「神西清」の項(=全集未収録文)のプリントを配布して朗読し、神西文学に対する福永の評価をまず確認し、福永武彦編『神西清詩集』(東京創元社 1958)を回覧しました。そして、Ⅱ.神西の人となりを知るために、無二の親友であった堀辰雄の文学を江湖に広めようと新潮社元版『堀辰雄全集』(1954~1957)刊行のために心血を注ぐ神西の姿を、編集者の前川康男宛自筆書簡(写真版)を朗読することにより、浮き彫りにしました。その際特に、神西の繊細かつ実務的一面に光を当てました。配付した神西の自筆に接することにより、一層の親近感を持っていただけたら嬉しいことです。更に、Ⅲ.神西の『風土』評と『草の花』帯文(推薦文)を読み、福永文学に対する神西の高い評価を確認しました。最後に、Ⅳ.『神西清全集』(文治堂)全6巻は刊行されているものの、その研究は寥々たるものであり、早く高橋英夫『批評の精神』(中公選書 70.12)の中に論じられており、亦ロシア文学の池田健太郎による幾つかの随筆で、その人となりや訳文の価値が高く評価されているとは言え、この25年余りは、石内徹が年譜・書誌を中心に研究を進めている他には、ほとんど手がつけられていない現状を報告しました。
私自身は、神西に対する「未完成の大作家」という福永武彦や中村真一郎の評価に対して――これは、充分説得力のある見方なのですが、その一方で――神西と「鉢の木会(鎌倉文士の集まり)」で親交を結んだ中村光夫が「僕は氏の生涯を未完成と見る人々に必ずしも同意しません。氏はむしろはじめから完成してしまった精神の持主なので、氏の一生は完成という厄介な病気からどうやって抜けだすかという苦慮に費やされたようです」(『秋の断想』筑摩書房 77)と指摘していることに注目します。芸術家の使命は、作品創造(完成)の1点にしかないというスタンスを貫いた福永とは鋭い対立をみせていて、刺激的です。
神西作品として、まずは『雪の宿り 神西清 小説セレクション』(港の人 2008)から手にされることをぜひお薦めします。
- 最後に、福永随筆の特質を簡単に解説しました。幻想作家内田百閒の文学に親炙した福永の随筆は、時に(意識的な)虚構が混在しており、それが魅力のひとつとなってはいますが、年譜などで安易に引用を許さぬ点があり、単に福永の人となりを知るための材料では決してなく、内容と文体が緊密に結びつき、ひとつの世界を構成する(詩や小説と並ぶ)「独立したひとつの作品」であるという点を強調しました。この点は、2000年6月の第47回例会で、虚構を含まぬエッセイとの違いを論じる際に詳しく述べたことがありますが(「福永武彦のエッセイについて」)、今回改めてその点を確認しました。
⑤Kiさん
-
Miさんより神西清についての話を伺い、自分にとって未知の作家だったのでとても興味深かった。早速、図書館から「雪の宿り」を借りて読んでみた。応仁の乱を背景とした歴史小説
だが、考え抜かれた構成と緻密な描写が強く印象に残った。引き続き現代小説を読んでみようと思っている。
随筆集「別れの歌」の中では、清瀬の療養所で書かれた文章が興味深かった。「知らぬ昔」では、福永が大学受験を控えた高校3年のときにグリルのレコード係の娘に片思いをしたエピソードの語り口が絶妙で面白かった。屈託ない福永の青春時代の側面が伺えるという点でもいい文章だと思う。昭和27年9月に清瀬で書かれたということで、時期的には退所する前年で、追分にも出向き7年ぶりに堀辰雄に会った頃で将来的に少し明るさが見えてきた心象が反映されているのではないかとも思われる。これは「文学界」に掲載されていて、随筆と言っても全体の構成とか文章も相当練られているようで、たとえば女の子に片思いをしたのは事実としても、署名を読み間違えたとかの箇所は
出来すぎなので、フィクションではないかと疑われる。
「病者の心」は27年5月に清瀬で書かれ、「保健同人」に掲載されている。孤独と死についてのこの随筆は、福永の延べ7年間の清瀬での体験の総決算とも言える。発表されたのがメジャーな文芸誌ではないこともあり、福永が当時考えていたことがストレートに吐露されているのではないかと思われる。
清瀬での闘病体験がなければ、孤独と死を主要モチーフとした後年の諸作品は生まれなかっただろうということが改めて納得できた。
⑥Siさん
- 1.随筆「別れの歌」について
白状すると福永の随筆を読むことを私は、意図的に避けていた。私に取り「福永武彦」という名前から印象されるのはボードレール・マラルメの象徴主義に基づいて緻密な文学空間を構成する「文学者」であり、日本文学の伝統的な文壇などには、その私小説に対する軽蔑と同じようなものを持ってして距離を取っている「否=文人」というイメージであった。そのようなイメージに凝り固まらせた福永を愛した故、随筆集の存在自体が彼の文学に対するあり方と矛盾するようで「お金のために書いたのだろう」などと理由をつけて読まないでいたのだった。しかし、読み始めてみると止まらない。私の曲がった信念は何処へやら、夜を徹して読んでしまった。
まず驚いたこととして福永武彦は、偉大な文人であったということだ。加藤周一ではないが「雑種文化」として成長してきた日本文化である、その磁場の中心にいた福永のことである。漢詩を読み、マラルメを読みながら仏教美術について語る。文化的磁場には明治以来、海外から流入した文化資本を自己のものにするための試みを、その生をかけて行ったものの遺伝子を継ぐ人々が集まっていた。そのような磁場は、戦後において「不可能」となっていったように感じる。堀辰雄、室生犀星、神西清、中川一政……。純粋文化人の遺伝子を受け継ぎ彼らを顕彰した福永像が、この随筆には溢れている。それは、古き良き文化人たちの時代への「別れの歌」であり「喪の仕事」(mourning work)であったのかもしれない。
2.『影の部分』ドイツ語訳についての発表に関して
今回、会から寄託されました資料『影の部分』ドイツ語訳(2007)について簡単に発表させていただきました。
独文科出身の身として福永のドイツ語訳『草の花』(2012)が出る以前にドイツ語で彼の小説が翻訳されて出版されたという事情に大変驚き、私のドイツ語力が稚拙なのは重々承知ではありますが自主的に調べた結果、大変興味深い事実が明らかになり例会の場を借りて皆様との共有を図ろうという意図でございました。
次回例会において、内容に踏み込んだ発表もできればと考えておりますが未定です。
【当日配付資料】
- ①ドイツ語訳「影の部分」についての解説資料。発行経緯、訳者による福永武彦紹介、訳者紹介、フンボルト大学と森鷗外研究所について。A4両面、1枚。
②第一随筆集『別れの歌』書誌:初刷から第12刷までの刊行年月日、定価他、書誌事項を記したもの。A4片面1枚。
③福永武彦が『新潮日本文学小辞典』(新潮社 1968.1)のために執筆した「神西清」紹介文。全集未収録文A4片面1枚。
④神西清自筆書簡(新潮編集者 前川康男宛 1953.8.18記)複写。ペン書き便箋2枚+神西宛関連書簡便箋2枚の画像と註釈。A4片面3枚。:『堀辰雄全集』編集委員としての神西が、同じ編集委員の中村真一郎、福永武彦、谷田昌平の3者で決定した事項に対して、自らの賛否を箇条書きで列挙している。
⑤神西清の省略版『風土』評(初出「日本読書新聞」1952.10.13掲載 『神西清評論集 下巻』文治堂 1976.1より)と元版『草の花』帯の推薦文。A4片面1枚。
⑥「文学フリマ」(今秋)のための、小冊子発行計画書。内容概略、論考・紹介文執筆者、表紙・挿絵の作者とその画像。A4片面1枚。
⑦鬼子母神・護国寺周辺地図。11月3日に予定されている文学散歩の経路。A4片面、1枚。
⑧2014年度会計報告書。A4片面、1枚。
提供者:①Si、②~⑤Mi、⑥Ko、⑦Ma、⑧Sa
【回覧資料】
-
①『詩と小説のあひだ』神西清(白日書院 47.9)石川淳宛毛筆署名本。石川淳旧蔵本。
②『灰色の眼の女』神西清 (中公文庫 76.9) 解説 三島由紀夫:神西の「雪の宿り」を絶賛し、現代の似非歴史小説家の諸君は「三拝九拝するがよろしい」と断じる。
③『神西清詩集』福永武彦編 (東京創元社 58.3)中村真一郎宛神西百合子毛筆署名本
中村真一郎旧蔵本。:百合子夫人より預けられた神西の詩稿133篇を福永が整理し、その中から52篇を厳選して、自ら解説を付した。解説文は、福永全集第17巻に収録。
④『秋の断想』中村光夫(筑摩書房 77.1) 井上靖宛ペン署名本:「鉢の木会」での友人として、亡くなった神西への追悼文を収録。「未完成な大作家」という中村・福永の評価に反対している。井上靖旧蔵本。
⑤『批評の精神』高橋英夫(中公選書 70.12)福永武彦宛ペン署名本 60年代に書かれた神西清論として貴重。福永武彦旧蔵本。
⑥『人物書誌大系23 神西清』石内徹編(日外アソシエーツ91.6)
⑦『複製 神西清翻訳原稿Ⅳ チェーホフ作「三人姉妹」』(神西清研究会08.1) 限定50部本 非売品:神西清自筆翻訳原稿の写真複製本。
⑧神西清自筆葉書 新潮編集者前川康男宛 1953.7.18 ペン書き1枚:『堀辰雄全集』の編集委員に川端康成を加えることに関して。
⑨中川一政自筆葉書 知人宛 1961. ペン書き1枚:『別れの歌』の装幀をした中川の筆跡を見るために回覧。独特の魅力がある。
⑩『櫟の木に寄せて』書肆科野 77.8 普及本提供者:
⑪『櫟の木に寄せて』書肆科野 76.9 限定85部本
⑫『小説の愉しみ 福永武彦集』 講談社 81.1
⑬2012年の軽井沢・追分文学散歩の際に立寄った文学館、食事処などのパンフレット
⑭ 同上、玩草亭や「油や旅館」の画像(パソコンで提示)
提供者:①~⑨Mi、⑩~⑫A、⑬・⑭Si
【その他】
- 会誌第11号の原稿募集。
既にメールや掲示板でもお知らせしていますが、10月末刊行予定の会誌第11号用に以下の原稿を募集しています。
・会員短信 400字~800字。内容は自由。第10号を参考にしてください。
・随筆 400字×10枚~15枚。福永作品に関ることであれば、内容・形式は自由。
ともに、締切りは9月初旬となります。ご質問などありましたら、三坂まで。
- 福永武彦自筆草稿を冊子にしました。
第一随筆集『別れの歌』に含まれる随筆「閑居の弁」(200字×15枚完 ペン書き)、「石仏その他」(200字×10枚完 ペン書き)2篇の福永自筆草稿をスキャンし、オールカラーの冊子(A4判、26ページ、本文には写真集に使われるコート紙を使用)を印刷所に頼んで、個人的に作製してみました(画像参照)。簡単な註釈付き。限定15部。「閑居の弁」本文中に言及されるBretonの“L’Art
magique”(『魔術的芸術』)のフランス語元版(1957)の表紙写真、或いは日本語訳本(河出書房新社 2002)の表紙写真のうち、どちらか1点添付。
7月例会にて、希望者にお分けしました。残部数冊ありますので、購入希望の方は、三坂までご連絡ください(送料込み、2500円) 売り上げの半額を、会の財源として当会に寄附いたします。増刷はしません。

 第152回例会・平成27年度総会 第152回例会・平成27年度総会
【日時】2015年5月31日(日) 13時~14時30分
【場所】川崎市国際交流センター 第2会議室、参加:12名
上記の日時・会場にて総会を開催しました。
①口頭にて前年度会計報告の後 ②新運営委員を決定し、続いて ③今年度企画を提案して、各々承認されました。
総会終了後、中・短篇集『世界の終り』(人文書院 1959.6)より、「影の部分」(1958.7)・「世界の終り」(1959.4)の2作品を採り上げて討論しました。今回で『世界の終り』の収録作品の討論は終了します。
以下、発言者自身による要旨・感想を掲載します。
【発言要旨・感想】順不同
①Maさん
『世界の終り』を読む
- 「世界の終り」は印象的な独立した一行で始まる。
(夕焼けが美しい)
その言葉に呼応するように、次ぎの行が追いかける。
(夕焼けが気味の悪いように赤く燃えて美しい。)二行目はそのまま(こんな美しい夕焼けを私は今迄に一度も見たことがない。)と続いて、「私」という人物、町なかを歩いている一人の女の行動と内面の意識へつながってゆく。
そしてこの非人称の詩的な一行は、段落ごとに別のあらたな呼びかけとなって立ち上がる。あたかも「もう一人の私」から発せられたかのように返答し、自問自答し、時には全く別人格の他者のように威嚇し命令し、暗示し唆し恐ろしい宣告を下す。
四部に分けられた小説の一と四、「彼女」のタイトルでまとめられた、物語のはじまりと終りの進行をリードしてゆく。
私はこの詩的ではあるが詩ではない一行が気になって仕方がなかった。
この言葉を発する主体は捉えどころがなく、「もう一人の私」と限定することができない不気味さをはらんでいる。あるときは「彼女」の意識を呼びおこす呼びかけであり、暴力的な力を持った声である。もう一人の私に出会わせ、業火の地獄に引きずり込む。
今回はこのリードの一声(行)を発するものの正体を捉えたい。
物語全体で何行の声があるのか数えてみることにした。一つ一つの言葉と「私」である「彼女」との関係を考えながら。
抜き書きしてみると、いくつか興味深いことがわかってきた。その数には意識的なまとまりが感じられた。作品の構造も緻密に考え抜かれた構成をもつことが見えてきた。
思いがけない発見だった。
一章と四章は「彼女」、「彼女」(続き)というタイトルで、冒頭の形式で最初と最後を締めくくる。二章は、「彼」であり、彼女の夫であり地方都市の医院を営む若い医師の視点で徐々に異常さを増す妻の行状が語られる。学会で三日間出掛け家へ戻る車中の一時間である。
三章は「彼と彼女」、澤村駿太郎と多美(旧姓黒住)の、主人公二人の名が初めて明かされる。「その日」(学会から彼が戻る、小説の現在時間)を起点として、彼と彼女が初めて出会った過去からの経緯が,几帳面な時間軸の計算とともに再現される。「死の島」の時間軸を想起させるが、作家の目を通し小説全体が俯瞰されると言おうか。
そして、終章四の結末に向かって、「彼女」「彼」「彼女と彼」の三つの物語の時間は切迫の度を深め収斂されてゆく。
一行のリードとリードの間隔はますます短くなり緊迫感を強め、合体する。
そこにあるそれは。成就あるいは作品のタイトルが示すものである。
私が便宜上「リード」と名付けた一行の声の数を、私は全体で50と数えた。
一章に20、四章に30である。偶然ではないと思いたい。
この声の醸し出す効果は大きい。
抜き書きをすると詩的ではなく、むしろ散文そのものなのだが、次に続く彼女の内面の声と相まって作品のなかで木魂し魔術的な力を発揮するように思われる。
当時は精神分裂病と呼ばれた統合失調症、あるいは離人症などの精神疾患の妄想、幻覚、幻聴、あるいは自分がもう一人の自分を見るドッペンゲルガーの現象を、狂気の内側からつかみ取り、言葉の力で体感させてくれるような力を感じる。
音楽的で怖ろしいほど美しい映像である。
戦争と病との長い伴走の間に、福永さんは心理的に病者の達する深さまで降りてゆく体験をされただろう。当時流行の兆しのあった精神医学にも深い関心を寄せ、学ばれたということだ。
「世界の終り」は、1959年2月に書かれた。(人文書院 新装版による)2015年6月の現在、56年も歳月を経たとは思えない古びないいのちがあると私は思う。
タイトル裏のエピグラム(忘れられた過ちによる死刑宣告。恐怖の感情・・・)ボードレール「散文詩草稿」との重要な関連を、会に隣席した若い人が耳打ちしてくれた。このエピグラムも気になる一つであるが、考えおよばぬまま放置していた。ぜひいつかまとめて聴かせてほしいものだ。
『影の部分』について
- 今回採り上げた二篇の作品のうち「世界の終り」に多くを割いたのは「発見」があったからだが、「影の部分」を軽んじたわけではない。しかしところどころに挿入されるカタカナ書きの主人公の内面の意識の叙述以外章立ての区切りもなく、小説はだらだらと続く。あまり完成度が高いとは言えない。
福永にしては平凡な市井の生活の中で娘が小さいときから共に親しく交際してきた若い未亡人と、今は妻帯者となっている男との関係と運命を、淡々とした筆致で描いている。
それなのに、最初の頁から「これは小説ではない」「僕は小説のようにこれを書くことが出来ない」という断り書きを再三、書いているのはなぜだろう。
私はこの断り書きを、小説を「作品」として際立たせるための逆説的技巧と捉えてきた。が今はよく分からない。
今回心に残ったのはこの言葉。
「人は決して急に、掌を打つように、分かることはない。それはいつでもゆっくりと、しかし確実に、健康な子供の背が伸び体重がふえるように、わかって行くのだ。・・・これが小説ならば、ーー以下略ーー本当の現実は、何かが少しづつ分かって行きしかも何の解決もないことそれ自体のうちにあるのではないだろうか。僕の書くものは小説ではない。」
小説の運命にかぎらず、この作品のビターな味わいには汲み取るべきものがあると思う。
この現実認識の苦さがあって、小さな娘を相手にままごと遊びの客人をつとめる男と女の姿が逆光のような強い光を放って心に焼き付いている。
②Kuさん
『世界の終り』について
- 『世界の終り』については、会報第19号で、Taさんが、ヨクナパトーファ・サーガに倣って、福永も「北海道の奥地に架空の町を設定」したとのべておられます。Taさんの説を批判するならば、福永は疎開先として北海道に来たわけであり、この小説に出てくる「寂代」も「弥果」も部外者の眼で見ているだけ、ということもできます。しかし、何となく、多田さんの説も面白いと思いました。
③Kiさん
『影の部分』について
- ・福永らしさの感じられる小説で好きな作品だ。
・主人公と麻子、幾子との関係が「死の島」の相馬鼎と相見綾子、萌木素子の三角関係に相似している。相馬は綾子に惹かれているように見えて、実際には素子を愛していた。
『世界の終り』について
- ・「死の島」との相関がある。妻の一人称の視点は、やはり狂気を内に持った「死の島」の素子の「内部」に相似する。最後、駅で主人公を迎えた母が告げようとしていたのは妻の死か、あるいは一命をとりとめたのか明らかにされていない。「死の島」のラストと同様の読者の想像力にゆだねる手法。
・「あなたは私を幸福にしてくれなかった」という妻の訴えは、福永が妻澄子(原条あき子)から受けた言葉の反映がありそう。
・精神病理学的な描写に重点が置かれていて、それはそれで興味深いが、福永が作品を通じて何を言いたいのか伝わってこないもどかしさを感じた。「死の島」の素子は狂気を宿していたが、この作品の妻のような精神病者ではなかった。
④Naさん
『影の部分』について
- 光の部分は表に現れた明るいこと、そこには影の部分を内在しています。現実に起こった出来事のうちに、起こり得なかった影の部分があり、それは運命を決めることさえありえます。娘は、主人公の男性にとって、美しい母の影の部分と云えます。「鬼」や「未来都市」のように簡明ではありませんが、読者に様々なイメージを喚起できうるもので、福永氏らしい整然とした短篇です。
『世界の終り』について
- 夕焼けは、多美にとって、街を燃やし日常が失われていくことであり、自身の精神も損なわれていきます。多美の切迫した心理の詳細な描写は、著者が精神病理学を勉強していたことと無縁ではないと思います。精神の状態が変われば、自覚する世界も変わります。陰鬱で安堵が感じられないのは、著者の長い病床生活や北海道での体験の表れかも知れません。
「僕が決して技巧上の實験のためにのみ、批評家を眩惑させるためにのみ、小説を書いてゐるのではなく、心の奥底に人すべての持つ深淵を持ち、それを常に覗き見ながら、この無意識なものを虚構の世界に寫し取ろうと努力してゐることを、讀者は、僕の愛する讀者は、理解してくれるだろうか。」(単行本の後記、昭和34年5月)に著者の思いが要約されています。詩的な美しい文体で、四楽章から成る交響曲と捉えると音楽的でもあります。構成は緻密、小説の方法が確固としており、福永氏の重要な作品のひとつであると改めて実感しました。
⑤Siさん
『世界の終り』について
- 「人は自分自身について、もっとも知るところが少ない」という常套句は、人口に膾炙した安易な精神分析とともにつまらないものである。しかし福永の良くできた短編に限ってはその事実が、小説としての構造の中に組み込まれるとたちまち動的意味を持ち出し、作品を優れた「人間の根源的な存在」への問いかけとして成立させてしまう。その意味でこの「影の部分」と「世界の終り」は大変成功した作品であると感じる。
福永作品において、登場人物の典型像の一つとして自己の存在を、己の力のみで措定しようと躍起になり無意味な回り道をしながら周囲を傷つける男というものがある。彼がたどり着こうとしているのは、いつも彼自身には謎としか思えない「女性」である。男の視点から語られると、その「彼女」は当然常識で計りえない存在であるからにして「病んで」みえる。彼女の悩みは、男がいつも了解している現実を突き崩す。『女性は男性の症状である』という精神分析家ラカンのテーゼがこれほど有効に響くものはない。「世界の終り」では、確信犯的にフロイトが登場する。「私の中の不在」、「私の中のもう一人の私」が現実(恐ろしいことに、小説では多美の語りによって第二・三章で語られる駿太郎の視点の現実が、「たった一つの」現実ではないという現実が提示される……現実が夢でない保障などないのだ!)に生きている多美を脅かす。その姿は、駿太郎のうちに反射して彼をも脅かしもするし、それは彼にとって蠱惑的でもある。
そのような多美は、病理学的に言えば統合失調症・離人症(解離性同一障害)の典型例である。また「私が私でなくなる」ことに悩まされる彼女は、自己の存在を悩んでいるともいえる。彼女は作品を通して「ほんとうの私」を追い求めているようだ(その願いが、「私の中の不在」の語りを成立させているかもしれない)。彼女は徹底して内向的であり、外部と関係を結ぼうとしない。駿太郎は、彼の信じるものしか信じておらず(無責任にも、その「信念」で彼は多美を汽車から下ろすのだ、寂代行き切符を持っていても多美が寂代で降りたかったかどうかわからないのだから)、かつたとえ妻であっても他人の精神を了解することはできないという、凝り固まった精神の持ち主だ。彼は彼女と正反対に「ほんとうの現実」(科学的・第三者の視点から見た現実)にすがりつく。外部との関係にのみ、自己を見出しているともいえる。この対称性が揺らぐ瞬間を描いたのがこの作品だ。
そこでは、なにが「ほんもの」かがわからなくなる。それゆえドッペルゲンガーの登場は、象徴的である。「ほんとうの私」も「ほんとうの現実」もありはしない。その揺らぎの瞬間が、例会での松木様の指摘通り交響曲の構成で、高度に数学的で詩的な構成(ボードレールのエピグラフが示唆的だ)の元、語られる。血・もしくは子宮の中の赤色、関係性を紡ぎ出す可能性であった子どもの流産……、象徴的なものを散りばめ「私は思い出す」と「私は見る」との距離を表したこの作品は、一編の詩のようだ。
⑥Miさん
『影の部分』について
- 幾子・麻子母娘には、当時福永の身近に居た岸野愛子・礼子母娘の影が濃厚に反映していると思われます。歌人の岸野愛子は、武彦の母トヨの一番上の姉ヒデの長女ですから、武彦の従姉になります。「身内のことで申し訳ありませんが、このかた(註
愛子)ほど美しいかたには、お目にかからなかったと思いますね」「愛子と武彦とは、愛子が年長ですし耳にしませんでしたけれども、礼子のほうは、年が武彦に近いのですね。それで、「礼子を、将来はお嫁さんに」と、周りではそういうことを言っていたと耳にしたことがあります」「彼が最も心を許していて、自由に言いたいことを言い合えたのは、岸野愛子と礼子だったと思います」「(貞子夫人との)折り合いが悪い----いや、そりゃそうだと思います。当り前だと思います。貞子さんにしてみれば全く新しい環境の中に、病人を抱えて、いつまで生きられるか分らんような病人を世話しながら親族を離れて生きようと決めたのが、しゅうとめと小じゅうとめがいるところになったわけですから。そうでなくとも新婚なら避けたい環境でしょう」(秋吉輝雄講演「堀ノ内時代の福永武彦」2010より)。
愛子の歌を2首挙げておきます。
・汝が命断たむてだてをめぐらせる このむね知れや知らであれかし
・ときの間に日は缼(か)けつくし光なき劫初(ごうしよ)の空を風冷えわたる
本文異同表を作成して気付いたことは、元版(1959)→文庫版(1971)で手入れを行ったにも関らず、全小説版(1974)で元に戻されている(=元版と同文)箇所が13箇所もある点です。文庫版に於て、編集者が勝手に手入れを施した可能性があります。
『世界の終り』について
- この自筆草稿は、私の手許にあります。2003年末の銀座松屋の古書展に於て、本郷の大山堂のガラスケース内に見出したもので、翌2004年1月9日に同店へ出向いて入手しました。紀伊國屋製200字詰原稿用紙に194枚。惜しむらくは、原稿1枚(151枚目)のみ欠で、価格は40万円でした。
その5年ほど前から、福永自筆色紙や草稿が市場に目立って出廻り始め、「死の島」の連載稿がバラバラになってあちこちの古書店の目録を賑わしていましたし、「告別」(400字×164枚)や「形見分け」(200字×139枚)は七夕古書大入札会に出品され、各々相当の値で落札されていました。他にも「海からの聲」や「古事記物語」、「廃市」や後期短篇(「風雪」、「湖上」や「大空の眼」など)が、各々東西の横綱とも言えるG堂やN書林の目録を飾っていました。この「世界の終り」も、同様に市場に出た品の一つです。当時の状況の一部は、「福永武彦研究第6号」(2001)に、「古書目録に見る福永武彦自筆資料」として御報告してありますので、御覧ください。
その草稿には、1ページに0箇所~15箇所ほどの手入れがあり(書き直し、追加、削除等)、これは当時の草稿として―例えば「夜の時間」などと比較して―特に多い方ではなく、ページごとの入れ替えや節の順序変更など、大幅な手入れもありません。草稿以前のメモ段階で、周到な準備があったことをうかがわせます。
本文異同表を作成して気付いたことは、初出(「文学界」1959.4)の本文に校正ミスが多いという点(明確なミスだけで9箇所)と、一部分が新かな・新字になっている点です(他は旧かな・正字)。原稿を確認してみたところ、その初出箇所の文選工は「桜田」であることが判明します。
【当日配付資料】
①「影の部分」本文主要異同表(初出→元版→文庫版→全小説版本文異同表)A3表裏1枚
②「槐の木蔭 第2号」(福永「にほひ草」初出)A3片面2枚
提供:①Miさん、②Aさん
【回覧資料】
①『我思古人』(堀辰雄版三十部本 福永武彦による巻末「補記」/堀版『我思古人』には、100部本と30部本の2種があり、この30部本は稀覯本。その内容と2種の違いについては、当会HP「玩草亭日和 第32回」に詳述してあります。)
②福永武彦直筆「我思古人」印譜一部本(帖仕立て。)
③「影の部分」ドイツ語訳(2007) 会の資料として、Siさんに調査・保管を依頼
④福永武彦年譜(1918-1979) 宴会の席にて年譜ファイルを一部の方に回覧。
提供:①・②Aさん、③・④Miさん
 第151回例会 第151回例会
【日時】:2015年3月22日(日) 13時~17時
【場所】:川崎市平和館 第2会議室
【参加】:12名(内院生1名)
Ⅰ 中・短篇集『世界の終り』より、「死後」・「鬼」の2短篇を採り上げて討論しました。
Ⅱ 福永武彦年譜の作成途中における報告がありました。
Ⅲ 特別例会(菅野先生ご講演)の文字おこしの途中経過報告がありました。
以下、Ⅰを中心に発言者自身による要旨・感想を掲載します。
○「死後」について
- ・「死後」はそのタイトルに違和を感じていた。冒頭に登場する川辺の一匹の蜘蛛と、末尾の蜘蛛の幻影。その間に語られる主人公の大学の哲学講師の現在と過去の生のありようと内なる意識。「ある決意」をし、日常からエスケープする主人公。
「死後」とは、彼がしばしば陥る現実が死後のように感じられる意識の陥穽であり「魂のない、平面的な、微小な『生』のかたまり」である平板な「日常」である。現実が「死後」であり、死後もまた「現実」に似た虚妄の「生」であるなら、「僕」が望む「虚無、絶対の、輪廻もなく転生もない、完全な虚無」は死後にも存在せず、僕の死ぬ理由は失われ「死後」というタイトル自体が矛盾をはらんでくる。
前半の蜘蛛と一体化した彼の「待つことだ。待つこと以外にはなにもなかった。」という意識は何を指すのか。生そのものではないのか。「待つこと」は、中編『冥府』からも響いてくる。
この短編は地味で静かだが幾通りもの読みを誘う。逆説的な私の読みでは、今まで自死に終わると予測された主人公は予測を裏切って、蜘蛛の屍を仮象として実は日常に戻ってくると思えてくるのだ。(Maさん)
・短篇「死後」についての論文で、一番すぐれていると思ったものは、河田忠さんの『福永武彦ノート』(宝文館出版、平成十一年)に収められた論文である。河田さんは亡くなられ、論文が発表されて十年以上の歳月が経ったが、その価値はいまだに色褪せない。特に、『夜の時間』と通じる点や、小説『幼年』が想起される点や、『愛の試み
愛の終り』を思わせる点がこの作品に見られるというご指摘は優れている。僕も、その手堅い仕事ぶりに嘆息せざるをえなかった。この作品を読むとき、次に後進のわれわれが考えることは、作品中の「蜘蛛」がどういう意味を持つかということなどであろう。(Kuさん)
・ひときわ印象に残っている「死後」に関して記したいと思う。
この作品は哲学的モノローグが中心となった、西洋的ともいえる形式を持つ難解でそれ故印象の深い小作品である。
主人公の見る一匹の蜘蛛が、彼の中で反響し生と存在に対する思考を誘発する。この小説で彼の対峙する「生」とは、偶然の、個人の意識や意志では統括できない、曼荼羅を思わせる盆踊りのような輪廻の渦である。それは個体性の剥奪されたのっぺらぼうのような生であり、東洋的な生である。主人公はそれに対し、自己の存在を、自分の意識によって確立しようとする。「世界は今の僕の意識にふさわしく作られている」との彼の独白は、あたかも「自分があるところのものであらぬもの」へと自己を投企するサルトルによる対自的存在の定義のようだ(福永がサルトルの翻訳もしていることは念頭に置かれるべきだろう)。常に今ある自己から離れて自分の意識が、ある違う自己を志向するという、このような対自存在によって、彼の生には存在の穴とも言える「無」がもたらされる。主人公は、その「無」を自己の存在確立の場として享受する。
この能動的・個人主義的な実存の定義は、まったく西洋哲学の王道を行くものであろう。哲学講師の主人公としては、当然の思考態度であろう。
しかし、この彼の意識が活動している地平はどこにあるのか。彼の意識が働く地平は?それこそ一般的であり、自己の運命を受け入れるしかない蜘蛛のような「任意に与えられた」生なのだ。「それも亦、生なのだ」という独白は、それ故悲傷的な響きを持つ。能動的であろうとする意識は常に、受動的・東洋的生に掠め取られてしまう。生は不可能となるのだ。
それゆえ、主知主義的主人公は、逆説的に「死」を志向することで、「生」を可能とさせようとするのだが、その思弁的態度によってさらに生から遠ざかる。
この小説が、混乱しあまり成功していないという印象を受けるのは、上のような彼による精神の軌跡、つまり生に対する認識の発展過程がまったく描かれていないことに依る。ここではイマージュの連続によって『風土』以来作者の追求した(また、堀・中村の創作における課題でもあった)「西洋的生と東洋のそれの対立」を描こうと試みられている。作者は諸々のイマージュや「生」や「魂」、「忘却」という抽象的な言葉に、あえてその二つの解釈を可能とさせることで主人公の混乱と危機そのものを描き出した。まるで小説自体が一つの渦となり、深淵の上の蜘蛛に読者を変えるようだ。
福永の描く小説の魅力とは、生と存在に関する深い洞察にあると私は思っている。この小品には、そのエキスが濃縮され原石のように輝いて見える。私は一見洗練されていない、ナマの洞察が現れるこういった作品を好む者である。(Shiさん)
・河田忠さんが「福永武彦研究第3号」に寄せた『短篇「死後」ノート』の中で、"<死後の観念>の追求自体がこの短篇の主題であり、作者福永における生の実存の追求にほかならなかったといえよう"と述べているのに同感で、「世界の終り」などの作品同様、異常心理を描くことにより日常生活では認識し難い生の実存を浮かび上がらせるのが福永の意図だったと思う。「生」は決して連続してあるのではなく、日ごとに転生するのだ、そしてその輪廻から解放されるために死ぬのだという主人公の認識は仏教的と感じた。(Kiさん)
・僕の死の理由について終盤で「不断に緊張した生の一つ…また一つの断片…その煩わしさに僕は耐えられぬ。僕が望むものは虚無、絶対の、輪廻もなく転生もない、完全な虚無なのだ。」と言ったはずが、最後に自身であるところのものである”輪廻を象徴していたはず”の「蜘蛛の屍」を見るというのは一体どういうことか。輪廻を否定しているのか、肯定しているのか。それとも読者に考えよと言っているのであろうか。(Hoさん)
・執筆は1957年8月。4月より(学習院に加えて)母校に出講し、自身の日常生活や体調は順調な時期です。しかし、作品読解の際、次の3点は念頭に置いてよいと思います。①前年より、ゴーギャン伝の執筆を始めていること、②「当時新聞紙上を騒がせた、或る大学講師の不可解な失踪事件にヒントを得ている」という記述(『全小説 第6巻』「序」)、そして③5月末に、中村真一郎夫人の新田瑛子さんが自殺していること。
「人道を見下ろす喫茶店の硝子張の二階で、椅子に凭れ」ながら、行きかう人々の顔をいつまでも眺めることを好む30代の大学哲学講師。生を反芻し、輪廻も転生もない完全な虚無を望む彼の身体は、しかし硝子張りの箱に守られ、安全にそこに「在る」。彼にとって、現に「在る」ことに意味はなく、在らぬものを求めて硝子張りのこちら側でさまざま思念する(meinen)ことが生のようです(「魂が真実で日常が虚妄なのだ」)。彼には、日常に生はなく、虚無もまた、ないでしょう。彼は、この世の外(“Anywhere out of the World”)に虚無(=生)を求めて、永遠に冥府を彷徨う他ない単独者と言えます。その姿は、ゴーギャンにも、そして作者福永にも通じるものなのは、見やすいことです。
初出(57)→元版(59)→文庫版(72)→全小説(74)の本文異同を調べたところ、元版→文庫版の際に一旦表現を変更していながら、全小説版でまた元版と同一表現に戻している語句が4箇所あります。これは、文庫版での語句の変更が、福永ではなく編集者によるものだったからかもしれません。一般に、文庫版本文には、ルビを含めて、福永の意に満たぬ編集者の手入れがあると考えられます。(Miさん)
○「鬼」について
- ・「鬼」は、作者自ら作品中で種明かししている通り『今昔物語集』に材を取り、今日的合理的解釈と推理を加え福永流の主題にまとめ上げた作品。後の長編『風のかたみ』につながる、「腕ならし」(再版後記より)の意味があっただろう。読者としては演奏家に胸うちでなにやら呟きながら福永流の演奏を愉しませてもらったというところ。
今後は、中村真一郎と『源氏物語』との関係のように、福永と『今昔物語』との関係を時おり意識して考えたい。(Maさん)
・冒頭に今昔物語の一話を小説風に翻案した短篇を置き、間に今昔物語に登場する「鬼」についての福永の解説を挟んで、最後にミステリー風味の脚色を加えた短篇が続く構成の斬新さが特徴的であり、一般読者を意識した福永の工夫が感じられる。西田さんが「会誌9号」の『「鬼」論』で述べているように、「鬼」の1年前から発表されている加田怜太郎名義のミステリーとの関連が大きいだろう。また「子どももの」小説の系譜としても位置づけられると述べているが、納得できた。(Kiさん)
・福永作品として、珍しく、また少しだけ不自然に感じたが、主人公である男女の出会いが非常に動的に描かれ、映像(映画)向きに思える。
他の作品であれば、宮中の廊下ですれ違う(あるいは片方が笛や琴等の楽器を演奏していてその音を辿ると出会ってしまう)等、もっと静的な場面の方が多かったように思う。(Hoさん)
・平安時代の昔から、百鬼夜行や鬼に女が食べられる説話などが知られており、鬼は怖ろしい存在とされてきました。飢饉や戦乱での多くの死や行方不明は、異界から現れた鬼の仕業と考えたのかも知れません。しかし、この世では鬼だけが怖ろしいわけではなく、人こそが残酷で浅ましく、鬼より恐いことがあるようです。
童の姉が、哀れな死にかたをした女を慰めるには、殺してしまった悪い女に仇を討つのでなく、死んだ女のために佛を念じてあげると話しますが、これは日本人の普遍的とも言える優しさでしょう。大衆誌「キング」に載せるために執筆されたこともあり、福永氏の力量を示すとともに、確りとした格調ある短篇だと思います。(Naさん)
【当日配付資料】
① 福永武彦と岩松貞子の結婚報告葉書と封筒の複写 A4片面1枚。
② 「死後」/「鬼」本文主要異同表(全版対照) A3表裏2枚。
③ 福永武彦年譜、1953年(三坂 剛作成/曽根博義・田口耕平既出年譜より1953)A4片面2枚。
④ 特別例会での、菅野昭正氏講演の後半部文字おこしプリント。 B4片面5枚。
⑤ 特別例会写真(参加者別に封筒入)
⑥ 丸谷才一随筆集より「画家としての福永武彦」 A4片面1枚。
⑦ 村次郎詩集『歸國』 複写、A3片面5枚。
提供者:①・②・③Mi、④Ko、⑤・⑥Ma、⑦Fu
【回覧資料】
① 『福永武彦ノート』河田忠著 宝文館出版 1999.1 「死後」論収録(「福永武彦研究第3号」初出)
② 『堀辰雄 福永武彦 中村真一郎』日本文学全集第17巻 河出書房新社 2015.3
③ 『「草の花」の成立 福永武彦の履歴』田口耕平著 翰林書房 2015.3
提供者:①Ku、②Ko、③Mi
 第150回例会 第150回例会
【日時】2015年1月25日(日) 13:00~17:00 参加者:10名(内院生2名)
【場所】川崎市男女共同参画センター(すくらむ21)
【概要】
- Ⅰ 中・短篇集『世界の終り』より、短篇「夜の寂しい顔」、中篇「未来都市」の2篇を採り上げて討論しました。
Ⅱ 福永武彦年譜の作成途中における報告がありました。
以下、Ⅰを中心に、発言者自身による要旨・感想を掲載します。
【発言要旨・感想】順不同(敬称略)
① Kiz氏
・「夜の寂しい顔」について
ユングの心理学におけるアニマ(男性の無意識にある女性像の原型)理論とミステリーを融合させた作品ではないか。謎(夢に現れる女性は誰なのか)を読者に提示して、ラストで意外性のある答えを提示するのはミステリーの典型。「群像」に発表されたが、純文学作品というより同時期に書かれた「鬼」や「未来都市」のような一般読者向き作品に近いと思う。
興味深いのは母親に対する彼の態度。中学3年生なら反抗期の真っただ中が普通だと思うが、「試験に落ちてしまえば、僕はうちに毎日いて、お母さんの顔ばかり見て、お話をしたり遊んだり出来るだろう」というのは、まるで小学生の感情。早くに母を失った福永には思春期の子供と母親との距離感が実感できていないことが窺えて興味深い。
・「未来都市」について
雑誌社からの「面白い小説」をという註文を受け、尊敬する純文学作家であるハクスリーの「すばらしい新世界」の枠組みを使ってエンターテイメント作品を書いてみようとしたということだと思う。同時期に書いていた加田怜太郎シリーズとは違うSF的なアプローチを試したかったのだろう。
私とローザは無事脱出できたにもかかわらずラストが暗いトーンとなっていて必ずしもハッピーエンドになっていないのは当初のままなのか、「文学界」や「小説新潮」に持ち込むときに変化したのか興味がある。あるいは、エンターテイメント作品とはいえ、単純なハッピーエンドにはできなかったのがいかにも福永らしいところなのか。
② Ku氏
この作品は、昭和三十二年に書かれた。ちょうど同じ年に、福永の師匠ともいえる堀辰雄の「驢馬」での僚友だった中野重治は「梨の花」を書いている。同じ「少年もの」ではあるが、内容が随分ことなる。
「梨の花」は、子供向けなのに、「天皇」が出てきたり「乃木将軍」が出てきたりする。子供向けらしくない。その点、「夜の寂しい顔」は、個人の名前が「クニ叔父さん」と「トシ子さん」しかなく、日本のどこにでもありそうな普遍性から内容も成り立っている。福永武彦と中野重治との差は、このへんから見られるのであろう。
③ Ko氏
・「夜の寂しい顔」について
主人公は少年と青年の狭間にあって、自分の意識下にあるアニマとの邂逅を夢の中で果たす。
そこには「河」から続く少年とその成長を象徴的に描くという手法がここにも採られていて、
福永の青少年期の主人公を描く一典型を、この作品から見いだすことができるのではないだろうか。
・「未来都市」について
映画評論家としての福永を、この作品には感じずにはいられない。
『メトロポリス』からの古典でもディストピアは崩壊して終幕を迎えるのは定跡であるし、SFにいかに純文学的要素を加味しようとしたか、という実験的な作品であると思う。
④ Na氏
・「夜の寂しい顔」
少年の孤独と自我、死と愛を描いた短編のひとつです。中学3年である彼のひとりで生きているような孤立感が、切実で現実味をもっています。その基底を成すものは、自然で率直なごく普通の生活であるように見えます。彼は勉強だけに向かえる環境にあり、裕福な立場にあると云えますが、父と姉を亡くしました。母が再婚したために自分から離れてしまった感覚を抱き、家族皆で過ごした時を懐かしんでいます。この位の年齢では、物事を純粋に単純に考えがちですが、一方で多面的に捉えることが可能になる頃でもあります。彼の大きな関心事は「存在の感情」であり、人間にとって本質的な問題である「存在の理由」について思い巡らします。「存在」という主題によって、母への思いや女性への愛をも含めて、作品が巧く纏められていると思います。静逸でどこか寂しい感じのする福永小説が私は好きです。
⑤ Mi氏
・「夜の寂しい顔」について。
初出(57.5)→元版(59.6)→文庫版初刷(71.6)→全小説版(74.2)の本文異同を確認し、異同表を作成、配付しました。全版に渡って、表現上の小さな手入れが多いのですが、そしてその「表現の小さな違い」にこそ(言葉の響きを含めて)、福永短篇を味わう秘密が隠されているのでしょうが、夢の中に出てくる女の人称が「私」(初・元)→「あたし」(文庫以降)に変る点などは、解釈上でも検討の余地があるでしょう。
Iさんが配付された、主人公の中学生や「未来都市」のローザ、アンナたちを想像で描いた絵(全身・顔)は、討論に「視覚」という新たな視点を導入する試みとして、新鮮で面白いものでした。よりマンガチックな絵なども添えてあれば、さらに刺激があったかもしれません。これからも続けて欲しいと思います。
・ 福永武彦年譜について。
作成途中の福永武彦年譜より2年分(1940、41)を採り上げ、既出年譜(源高根氏、曽根博義氏)と比較対照しつつ、『近さん 歩んだ道』・『マルドオロルの歌 画集』の内容に関して他、今まで知られていなかった事項をご報告しました。報告は、しばらく継続していきたいと考えています。
【当日配付資料】
① 「未来都市」参考資料一覧 A4表裏1枚。
② 「夜の寂しい顔」本文主要異同表(全版対照) A3表裏2枚。
③ 福永武彦年譜、1940年と1941年(三坂 剛作成/曽根博義・源高根既出年譜)
A4片面3枚。
④ 白水社「パブリッシャーズ・レビュー」1月15日号と白水社「ふらんす」14年12月号。(『友川カズキ独白録 生きてるって言ってみろ』の紹介文と友川「フランス絶望音頭 フランスと私」掲載)複写、A3片面1枚。
⑤「夜の寂しい顔」の中学生、「未来都市」のローザ、アンナ各人物のペン書き似顔絵複写。A4片面1枚。
⑥ 村次郎詩集『途上 或ひは標本室』 複写、A3片面5枚。
⑦ 戸村茂樹氏履歴 A3片面1枚。
⑧ 福永武彦自筆色紙(1枚は本物、1枚は贋物)の実寸複写。 A3片面1枚。
①:Ki、②・③・④:Mi、⑤:I、⑥・⑦:Fu、⑧:A 各氏提供。
-
【回覧資料】
- ① 菅野昭正氏の福永武彦研究会員宛色紙(特別例会時のもの 昨年末画像回覧)
② 山崎剛太郎氏の葉書(特別例会のお礼)
③ 玉英堂稀覯本書目第234号(『マルドロールの歌 画集』表紙画像が掲載)
④ 「週刊小説」1973年10月19日号 「現代の作家(86)」(秋山庄太郎)に福永武彦自筆色紙と右手を顎に当てた顔写真。酒席にて回覧(画像参照)。光太郎に「彫刻家になれる手です」と誉められた右手・指が強調されている。近頃、福永色紙の贋物がヤフオクにしばしば出品されている。
【関連情報】 
- Ⅰ. 『小山正孝全詩集』が潮流社より刊行されました。会員の渡邊啓史氏が、詳細な解説を執筆されています。残念ながらまだ手許にありませんので、内容の大略は、後日「掲示板」で御報告します。

Ⅱ.会誌第9号の表紙に迫力のある先鋭な絵画をお寄せいただいた友川カズキさんの新刊『独白録 生きてるって言ってみろ』が白水社より刊行されました。編集者がインタヴューしたものを纏めた「語りおろし」ですが、それだけに友川さんの息遣いがよく聞えてきます。ご希望の方は三坂までご連絡いただければ、2割引き(1600円)+送料でお届けします(署名入り)。
 第149回例会 第149回例会
以下の内容で開催されました。
【日時】 2014年11月23日(日) 13:00~17:00
【場所】 川崎市平和館 第2会議室 参加者:15名(院生・学生:3名、新規参加:1名)
【内容】
- 今回は、先日発行しました当会の「福永武彦研究第10号」掲載の緒篇に関して、1篇ずつ充分時間を取って意見交換をしました。その後、翌24日開催の「文学フリマ」への出展の最終確認と準備を行いました。以下、発言者自身による要旨・感想を掲載します。
① Na氏
・「草の花」とともに-福永武彦とわたし- を読んで。
会誌10号のなかで真っ先に読ませて頂いた随筆についての感想を報告します。まず著者の情感がしみじみと伝わってくる文と構成に感心しました。草の花を高校一年生のときに読んだことから話しは始まり、その頃に出会った本や書店に足繁くかよったこと、周囲には福永を知る人はまだ皆無だったこと、信仰のことなど、どれも清廉で心温まるものです。とりわけ、訃報がテレビのテロップに流れ、そして葬儀に駆けつけた際の記述は、体験した人ならではの貴重なものです。福永文学を愛する人にとって必読の随筆です。
・例会「会誌10号を読む」で感じたこと-読書と研究-
読書が、個人の愉しみ、思索、探求などに基づく行為であるにせよ、そこには人それぞれの読み方や読解が自在にあるはずです。一方、研究では作品を丹念に読み解くことが必要であり、論文となると目標(解明するテーマ)、明確な方法、客観性をもった視点などが基礎になると考えます。研究会では相互に意見を述べ合い、専門的なことも拝聴できるので、理解を深めるための恰好の場となります。以上は当然のことのようですが今回の例会において改めて実感しました。
会誌10号は表紙 戸村茂樹氏装画、内容ともに良い仕上がりでした(私のような新人が言うのは僭越ですが)。
-
- ② Ku氏
今回の会誌は、よく出来たものでした。論文二篇については、例会で批判的なことを言いましたが、各々良い内容でした。その際に述べた「事実と意見」については、僕自身にもはねかえってくる問題です。松村さんのエッセイ、とても面白く拝読しました。この会が、一層発展することを願っています。
③ Wa氏
青木さんの『幼年』別稿翻刻、貴重な資料を公開していただき、感謝の外ありません。完成稿と比較して興味は尽きず、この作品の成立過程を考える上で、大変重要なものと思います。研究上の意義もさることながら、読者としては、作者の模索を肩越しに垣間見るようで、嬉しく感じました。
また松村さんの『草の花』をめぐる随筆、お人柄をよく伝える味わい深い文章で、興味深く拝見しました。一読、『草の花』の作者が読めば、さぞ喜ばれたろうと考えました。
木下さんの「退屈な少年」論、大変面白く読みました。論文らしい論文、それも原稿用紙 40 枚という長さのものを書くのは初めての経験とのことでしたが、よく書けていると思います。「査読」にあたられた会員の方々の助言、指導も大きかったようですが
(御苦労さまでした!)、これだけのものをまとめた努力を、大いに買いたいと思います。議論の細部についてはなお整理と検討の余地があると思いますが、自身の考えを自身の言葉で語ろうとしている姿勢に好感を持ちました。
その上で、将来の検討課題も含めて、気づいたことを幾つか述べれば、第一にフロイト。少年の造型にフロイトの精神分析の反映を考察することは一つの考え方ですが、この作品の分析に有効であるかどうか。此処で死んだ母親を慕う心情は、必ずしも病的なものではありません。また作者には、ミンコフスキのようなフランス学派の精神病理学の方により共感を抱いていたふしもあります。夢や無意識についても精神分析よりは、むしろ多くの詩人、作家の描いた幻想の方が身近だったかも知れません。そうしたことも視野に入れた上で問題を設定するとよいと思います。
第二に少年の「退屈」。少年の断定的な口調に注目して、「子供」であることを拒否しながら「大人」になり切れない「少年」の心情を読み解くあたり、よく考えたと思います。そこで少し附け加えれば、此処での「退屈」には、後に「賭」の出ることから推して、恐らくは一篇の背景として、西欧近代の時代精神としての「倦怠」や「憂鬱」といった問題が設定されているように思います。自然を支配し (科学と技術の進歩)、社会が組織化され (近代市民社会)、生活が豊かになり安定する一方で、社会の秩序から逸脱した人々は、夢や狂気に逃れ、憂愁に沈み、また予測可能でない不確定な、偶然のものへの耽溺に生の意義を見出す。そこでNervalは「夢はもう一つの生である」と呟き、Baudelaireは「パリの憂愁」を歌い、Mallarmeは「骰子一擲」を書く。この作品の背景には、こうした「近代」の主題も影を落しているように思います。ただ論文後半の、この少年が現実世界に生きているという認識は、適確です。これより早く書かれた短篇「夢みる少年の昼と夜」で「夢みる少年」は空想の世界に生きています。
その外、聖書を引いての「原型探究」の解釈や、「妣の国」を踏まえた「風」の極の説明など、的を外しているとは思いませんが、やや議論を急いだように
― つまり小さな事柄で大きな問題を押さえようとしたように ― 感じました。しかし、こうした感覚は、いずれ書きながら覚えることだろうと思います。
最後に、第三、此処では「少年」に焦点を絞っての考察でしたが、そのことを離れれば、そもそもこの短篇「退屈な少年」とは、どういう作品かという問題があるでしょう。一方には父の再婚をめぐる挿話があり、他方には兄と恋人と兄の病身の余命短い友人をめぐる挿話がある。その二つを少年の挿話が繋ぎ、展開させる訣ですが、父の挿話は、恐らくは作者自身の父の問題の投影と共に、漱石の主題 (殊に長篇『こゝろ』) への示唆を含みます。後者は「遠方のパトス」の変奏と考えることが可能です。少年は退屈な日常を遁れるため、最初は誤って池に落ち、次には周囲を驚かせようと家出を試み、さらに父の拳銃を弄ぶ。行動は次第に過激になり、殆ど「悪」の意識の芽生えを見ることも出来ます。
短篇「退屈な少年」には、さまざまな問題が含まれていると思います。木下さんには、第二、第三の「退屈な少年」論を期待します。
私自身の「夢みる少年の昼と夜」の考察については、本文に述べた通りです。執筆を強く勧めて下さったMiさんと、好意的に読んで下さった会員の皆さんに、この場を藉りて改めて感謝します。
④ Kiz氏
・「幼年」別稿
福永研究にとって重要な作品である「幼年」の解釈について重要な手掛かりとなる研究者にとって貴重な草稿だと思う。中絶してから3年後に発表された作品との対比により、福永の小説に対する考え方の変化とか、いろいろなものが見えてくる可能性があるのではないかと思う。
・「退屈な少年」論
「夢見る少年」「幼年」「退屈な少年」の共通項として<夢>を抽出して、当時フロイトなどの精神分析の本を読みこんでいた福永が<夢>という無意識を題材として少年の内面を描くことで、福永自身が抱えていた失われた母への想いという大きなテーマに踏み込んだ作品であるということ、また母への無意識な憧れが、謙二の原型を求める遊びや賭けに結びついているという論旨は納得できた。謙二の内面イコール福永の内面に近いと考えると、福永自身の幼いときに失った母への思いというのはこうまで強いものなのかと改めて考えさせられた。
・「夢みる少年の昼と夜」覚え書き
福永が「夢見る少年の昼と夜」について全集序文に書いた「周到に考え抜いた作品である」ということと「多少とも新しい方向を開こうと試みた」の2点をキーワードとして論旨を展開させていて、全体がとても明晰で見通しがいいと感じた。少年の造形などにマラルメの反映が随所に見られ、この作品がマラルメの強い影響下で書かれた象徴主義的な短篇の試みであったとする論旨に説得力がある。
・エッセイ「草の花」とともに
高校一年の「草の花」との出会い、福永の訃報に接して軽井沢の教会に駆けつけたこと、研究会への参加、長い時を経て読み返した「草の花」の感想、晩年の福永の入信についての疑問と「福永の入信はあるべき自然な受容であった」という理解に至るまでを情緒深い文章で綴られていて、とても心に沁みた。
・「戦後日記」「新生日記」書評
日記と小説とを安直に結びつけることは作品を矮小化することになるということ、詳細な注釈の有用性について言及していて、納得させられた。索引については次回の会誌で実現させたい。
・「小説 風土」本文主要異同表
本文主要異同を調べることは、本文研究の基礎としてとても重要であることは認識しているが実際のところ、根気のいる作業は大変なんだろうなという思いがあったのだが、三坂さんにとって、異同表を作成する過程で福永の文章を味読できるのが大きな喜びなんだということが書かれていて、なるほどと納得できた。
・随筆集索引
研究者にとって有用性があると思う。今回結果として6冊中3冊の索引集となったのは、分量的に適当だったと思う。
・その他
会員参加の会誌ということで短信にもっと多くの会員に投稿してもらう工夫がいる。短信の執筆者紹介はいらないと思う。
⑤ Fu氏
1.表紙について
戸村茂樹氏(八戸出身、岩手大学特設美術科卒、63歳)の版画は白地に黒の樹木の版画でシンプルで説得力があり、いい表紙だと思います。選んだ青木さん、三坂さんの美に対する感覚が優れていたのだと思います。
2.『退屈な少年』論
木下幸太さんの初めての論文だそうですが、とても真摯に書かれていて良かったと思います。今大学院の1年生ですので、今後おおいに期待できると思います。前にも言いましたが、福永研究会は、他の中村真一郎の会等と比べると会員の平均年齢も若く、若い大学院の学生さんも研究に参加していて、活気があり将来が楽しみです。またその人たちを指導できる会長やWaさんもいますので、今後も研究を深めて、毎年の研究会誌に発表していくのが大切なドクターへのステップになると思います。是非頑張って下さい。
3.『草の花』とともに-福永武彦と私-
松村文子さんのエッセイ楽しく読まさせて頂きました。学生時代からの思いが伝わってきます。福永武彦の雑司ヶ谷墓地に、会員数人で行きましたが福永武彦のお墓は、普通の仏教のよくあるお墓だった、と記憶しています。キリスト教徒の墓地ではありませんでした。その点この文の通りではないかと感じました。
4.少年・呪文・神話
渡邊啓史さんの論文は、いつも論文としてきちっと書かれており流石と思います。注の付け方など勉強になりました。
5.『小説 風土』本文主要異動表や随筆集索引等は、研究会の地道な努力の象徴で,他の研究者にも大いに刺激になり、参考になると確信します。担当者の皆様お疲れ様でした。
6.私の意見としては、福永武彦研究会会誌をK大学新図書館とG院図書館へ寄贈したらいいのではと思います。G院大学で福永武彦は教授をしていましたので、現在の大学生、大学院生もその作品を研究する人もいると思います。大学図書館は、蔵書するのに、選書委員会を通さなければなりませんがOKが出た後は、本の管理がいいので、苦労してできた福永武彦研究会誌は、多くの教授や学生に見られ結果として福永研究会の評価も高まると思うからです。
⑥ Kin氏
今回の会誌は携わった箇所が多いため、一冊の本となったことに深い感慨を覚えます。今回は論文を掲載させて頂き、その作業の中で多くの人からアドバイスを頂きました。今回の経験は、私にとって大変意味のあることだと思います。改めて掲載に至るまでにご指摘を頂いた方と、拙稿を読んで感想をくださった方に感謝申し上げたいです。ありがとうございました。
⑦ Mi氏
Ⅰ.松村文子「『草の花』とともに――福永武彦と私――」
日ごろの例会で、筆者松村文子さんの福永文学に対する長年の親炙を、そして文学的教養と筆力を知っている私は、松村さんに「今度の会誌に、ぜひ随筆を書いてください」と頼みました。「いえ、私は研究者でもないし」と遠慮される松村さんに「いや、書けます。長年福永を読んでこられた松村さんにしか書けないことが」と少々強引に頼むかたちでお引き受け願いました。
お送りいただいた原稿を一読し「やはり、書いていただいてよかった」と、10年余り一緒に研究会をやってきた仲間の一人として、実に自分のことのような嬉しさがありました。このような文章こそ、「実のある文章」と言うものでしょう。福永的に言えば「これで、松村さんはりっぱに義務を果たされた」のです。短文とは言え、自らの生の証を、しっかりと刻まれたのだと思います。
ひとつ残念なのは、「福永の信仰のこと」の節で引用された、当会誌第3号の黒岩浩美氏の論考が、「国文学 福永武彦へのオマージュ」(学燈社 1980年7月号)掲載の加賀乙彦、源高根両氏との鼎談における貞子夫人の発言を、また雑誌「本のひろば」(財団法人キリスト教文書センター 1980年2月号)掲載の「福永武彦の静かな回心―井出定治牧師に聞く 伊藤義清」文中の記述を、ほぼそのまま引用しているにも関らず、その論考中に正確に明示していないために、松村さんがそれらの発言や記述を黒岩氏のお手柄として引用してしまった点です。しかし、この滋味あふれる随筆においては、これはほんの小さな疵にすぎません。松村さん、これからもこのような随筆を書き続けてください。
Ⅱ.渡邊啓史「夢みる少年の昼と夜について」のための覚え書
さまざまな刺激を受けましたが、その内の1点のみ記します。
論考中で、福永の1954年度講義の中から、マラルメとプルーストとの対比、つまりマラルメが空間的現象の定着を目指すところで、プルーストは時間的現象の定着に向う、それゆえマラルメが適切に置かれた1つの単語で内的現実を捉えるのに対してプルーストは一つの観念を捉えるのにも何百何千の語を用いる、という福永の講義内容を紹介されています。その箇所を読んで、昔、私自身が、福永の新出短歌を紹介・解説する一文中(会誌第7号「中村眞一郎書簡に見る一九四〇年の福永武彦」)で、福永が全小説第6巻「序」で述べている小説の創作態度に2方向あること――Ⅰ.観念を幻覚として凝固させる方向、Ⅱ.流れ行くものを内的リアリズムによって造型する方向――と関連させて、その2区分が各々俳句と短歌の区分と共通するものがあることを指摘しておいたことを思い出しました。そしてそれが亦、各々マラルメとプルーストの手法にも対応するものであることに、改めて気付かされました。
Ⅲ.拙稿「小説風土」本文主要異同表
『小説風土』の初出と初刊本の本文異同に視点を据えた既出の論考2篇を簡単に紹介しながら、この一覧が解釈上のヒント満載であることを概説しました。前号の『死の島』とともに、来年度以降、自らこの一覧を使用しつつ、『死の島』と『小説風土』に関して、多少の考察を試みる予定です。
【当日配付資料】
- ① 福永武彦自筆手帖 1953年/1954年より、「学習院大学での講義題目と曜日、時間、教室」が記された手帖表紙裏/冒頭部分の複写。A4 1枚。会誌第10号、渡邊啓史氏「夢みる少年の昼と夜」論のための参考資料として配付。月・金の週2回、各2コマという数に「ずいぶん少ない。今ではありえないでしょう。特別扱いだったのか」との感想が聞かれました。
- ②11月24日開催の「文学フリマ」で配布するチラシを確認。A4表裏・1枚。既刊の会誌と当会の活動が丁寧に紹介されています。
- 資料提供:① Mi氏、② Ki氏
【回覧資料】
- ①『夢みる少年の晝と夜』槐書房限定B版125部
② 福永自筆書き込み本3冊
・「MALLARME ?UVRES COMPLETES」1945年刊行 表表紙裏3ページと裏表紙裏3ページにABCインデックスの書き込みあり。本文にも多数の書き込みあり。
・「MALLARME selected Poems」1957年刊行マッキンタイヤ英訳 詩の行数の書き込みのみあり。 外国風景カラー写真挟みこみ1枚あり。
・「MALLARME par Lui-meme」1964年刊行 下線引きと少しの書き込みあり。
③ 福永武彦自筆俳句はがきの複写とその説明文。「ブロンドの幼女走りぬ/きつね雨 福永武彦 落款」。俳句は複写だが、落款は、『草の花』初刊本(新潮社 54)や『冥府』(講談社 54)の奥付検印に使用された印材の原鈐(げんきん 直接印影を捺したもの)。これは、「文学フリマ」で会誌9号、10号の2冊を購入した方への特典として作成したもの。
資料提供:①・② A氏、③ Mi氏
 第148回例会 第148回例会
以下の内容で開催されました。
【日時】2014年9月21日(日) 13:00~17:00
【場所】川崎市平和館 第2会議室 参加者:10名(学生:2名)
【内容】今回は、福永武彦の終生に渡る文学的盟友であった中村眞一郎の代表作『四季』を採り上げて意見交換をしました。中村著作への親疎はいろいろありながらも、改めて作品の魅力に眼を開かれた参加者が多かったようです。その後、11月24日に予定される「文学フリマ」への出展の確認、12月14日の特別例会の内容確認を行いました。以下、発言者自身による要旨・感想を掲載します。
【発言要旨・感想】
- (Kuさん)
- 『四季』を中心とする諸作品ですが、上品にできていると思いました。「老人」と「性」の問題も、正直で上品にできていると、思います。中村さんの全体像ですが、やはり正直な人という印象を受けました。そして、数多くのエッセイは、『火の山の物語』に限らず、よくまとまっています。それに、中村さんは、最期まで堀辰雄を裏切りませんでした。立派です。中村さんを慕う人が多いのも、なるほどと思います。
-
- (Oさん)
- Ⅰ.中村眞一郎『四季』を中心とした諸作品への意見
・『四季』
人間とは、その記憶の想起・反復作用によって過去を、そして自らの生を意味のあるものへと高めることではじめて完成されるのだ、ということを僕はこの作品から感じました。
「君の、或いは我々の余生は、死ぬためのものではなく、生きるためのもの――従来の無我夢中の突進的生活よりも、より深く味わいつつ、一生の意味を認識して、それに完成した形を与えるためのもの――なのだ」 第二章 夜の思想より。
そういう主題は福永武彦の作品にもよく見られるもので、例えば『草の花』では、「さて、僕は決心した。しかし恣に回想することは、しばしば人を誤らせ易い。過去の曖昧な印象を再び捉えるためには、それを紙上に書きしるし、自ら冷静に記憶を定着させて行く他にはないだろう。(……)僕はただこれをゆっくり書くことによって、僕の死ぬまでの一日一日を、心おきなく生きられればそれで満足なのだ」という風に綴られています。
しかし、この両者の記憶を結晶させる試みには大きな違いがあります。『四季』に於いては、それの多くは欠落しており、主人公とその青春時代の友人であるKとの再会という偶然的な切っ掛けがその試みの契機となり、その後も記憶を受け取り直す行為には何か契機的なものが必要とされます。それに対して『草の花』では全てが自らの内部から汲み取られます。この違いは、その主人公の過去との距離、失われた青年時代と現在との隔たり(または電気ショック療法などの中村真一郎の個人的な理由)によるものだと思われますが、しかし僕には(僕が今その青春時代を生きている所為も多分にあるでしょうが)、過去の美しい時間をその記憶から失うだなんてあり得ないように思えるのです。それを中村真一郎は頻りに論理を弄して、青年期の次の破局の時期によって青春の記憶が破壊されただの、云々と理由づけていましたが、僕には到底納得出来ませんでした(いっそ主人公は電気ショック療法を受けた過去を持つ、などという設定にしてしまえばよかったようにも思います)。青春の記憶は厳しい現実を生きる間に次第に色褪せていくがしかし、その思い出は心の底で結晶し、自らが不意とその魂の息吹を感じる度に浮かび上がってはその美しさで自分を慰める……、そういうものこそが僕には青春だと思われるのです(これは僕が若者だからかも知れませんが)。……つまり、あまりにも手法的なものが目立ち過ぎているように僕には感じられたのでした。が、記憶の復活が自らの生命の復活と密接に関わり、それによって一つの過去が生き生きと形成されていく過程は読んでいてとても心地が良く、この小説は素晴らしいものだと思えました。
・『恋の泉』
恋の泉は、主人公の現在が進行するのと伴って想起による過去の反復もあり、それらは主観的説明と客観的説明とで圧倒的な緻密さで書かれている上に、一つの現実に対する様々の人の解釈があって、尚且つその様々の人の慾望などが渦巻いていて……、現実、現在というものの複雑さを思わせます。
主題は「それが恋の泉のテーマだったわけじゃない。――私はこの泉から、またもや、新たに恋の水を掬む。しかし、異なるのは杯だけで、中の水は同じものなのだ。……」と主人公の嘗て書いた劇にあるように過去の主人公と現在の主人公との、過去に愛した女性と今愛している女性との、諧和の神秘でしょうか。それは僕にはプラトンの思想に近いように思えます、一つのイデアがあり、それを分有している今まで愛した女性たちの諧和というような。それは言い換えれば、愛の原型、最初に愛した人を求める源氏物語的な思いでありましょう。
そのイデア的なもの、愛の原型はこの現実の悍ましさによって腐敗し、輝きを失ってしまうところまでが、この作品には描かれています。幾ら追い求めても嘗て自分の願ったものは最早手に入らない……、そういう悲劇的な印象を僕は受けました。
・『自鳴鐘』
これは、今まで読んだ中村真一郎の作品の中(『四季』、『恋の泉』、『女たち』、と幾つかの短編をしか僕は読んでいませんが……)で最も僕の気に入っている作品です。上に挙げた三つ作品はどれも一人称小説ですが、これは三人称小説だからでしょうか。情人を持つ女性との不倫に溺れる男を主人公にしながら、その男の妻への愛と青年特有の潔癖的な正義とによってその夫の秘密を暴こうと現実の謎へ迫る大学生をも描くことで茫漠で巨大なおぞましい世界を、立体的、重層的に作り上げているように感じられ、僕は特にその登場人物の、愛と正義とを信じる大学生に好感を持ちました。彼はその純粋さで巨大な謎に満ちた世界へ挑むことになるのですが、その対比が彼の美しさと儚さ、現実の不気味さを際立たせていて、そのあたりが福永武彦の読者にも気に入られそうだな、と感じました。
心理描写の技術、様々の登場人物を動かし、そうして一つの世界を創りあげるその構成の手腕、などなどがとても高い水準で試みられている上に、彼の文学的主題がバランスよく組み込まれていて、今まで読んだ中村真一郎の小説の中でこれが最も素晴らしいものだと僕には思えました。
Ⅱ.全体的に「中村の人と文学」 について
僕には「中村真一郎の人と文学」について語る上で、大きな欠落があります。というのも、中村真一郎を語る上で欠かせないことに、彼の王朝文学への傾倒、漢詩の知識、それらをもとにした試みがあるようですが僕はそれを殆ど理解していないのです。だから僕に語れるのは、「西洋的手法(心理主義的手法、想起的手法)を用いた小説家、中村真一郎」についてとなってしまうのです。
……中村真一郎の小説の特徴としてまず思い浮かぶのは、そこに自然描写、情景描写がありはするもののそれはあまり具体的なものではなく抽象的なものであることです。これは西洋の心理主義小説と共通するもので、その頁を埋めるのは緻密な、そして理性的な心理の分析、その記述です。その心理の動きによって恋愛心理小説の祖と言われる『クレーヴの奥方』は普遍さを有していて、いつ読んでもその登場人物たちは瑞々しいまま、僕らの内部に生き続けます。次に思い浮かぶ特徴として『四季』に顕著な記憶の作用があります。現在に於いて何かを切っ掛けにして過去の記憶が蘇る作用を、彼は『夏』では夢の氾濫と呼び、有効に活用しています。それもまた普遍的な人間精神の働きであり、心理描写の手法と合わさってその作品内に一つの生きた精神を形成します。
彼は常に人間の精神へ焦点を当てて小説を書いています。そうしてその人間の内部の愛もまた作品の主題とされています。崇高なものへの憧憬と、様々の女性との交わり……、その果てしのない試みは幼くして亡くした母への愛、自殺によって喪われた妻への愛を求める悲劇的なものなのでしょうか。その決して叶うことのない思いを、満ちることのない渇きを一心に求め続けることをしか出来ない空虚な魂、それが彼の姿であり、彼の信じる人間像なのでしょうか。
-
- (Naさん)
- ・「恋の泉」と「四季・春」
例会での討論作品として、「四季・春」が採り上げられましたので、この夏、まず「恋の泉」を、続いて「四季・春」を再読しました。
「恋の泉」は私が10歳代の終わりに初めて読んだ中村眞一郎の懐かしい作品です。「春」は1975年の発刊後すぐに買い求め読みました。この2冊は長年、書棚に置いてありほぼ40年ぶりに読み返したことになります。読む前の第一の関心は、2作品をどの程度、どのように記憶しているかであり、第二は、読了後に一体どのような感慨を抱くのかということでした。もし研究会で「春」を採り上げなかったら、熟読することはなかったでしょう。ですから、出現しなかったかも知れない経験が、貴重な体験として実現することになったのです。
「恋の泉」については、「私」と「若い混血の女性」を巡る男の恋の物語であることは憶えておりました。そして読み進めると、19歳頃はじめて読んだ時に「中年の男は、こういう恋をするものなのかと真面目に受け止めている自分」がいたことを想い出しました。読書において長い歳月を経ても記憶していることがあるのです。
記憶はその人間と人格を支えており、記憶がその人間を規定しているとも言えるでしょう。人間にとって記憶こそが、ほぼ全てなのかも知れません。しかも、その記憶は定着しなければ記憶として残らないのですが、忘れていたはずの記憶が何かの折に急に出てくることもありますし、誇張された記憶、眠ったままの記憶、無意志的記憶もあるでしょう。
「春」に関しては、避暑地での男の回想を描いている作品であることは記憶していましたが、ストーリーについてはあまり憶えておりませんでした。それは単に忘れてしまっただけでなく、20歳の当時の私には、50歳の男が現在=1975年から見た30年前の過去を回想する物語の意味するものが解らず、記憶に残りにくかったのかも知れません。
今回、「春」を読み始めたとき初めは冗長な感じがしましたが、次第にその感覚は失せ、過去の記憶をひとつひとつ辿るような緻密な描写は美しく、時間と空間の構成は絶妙であり、氏の独自の世界が展開されていました。回想を通して記憶を甦らせ、人生を再現しようとする願望を描いているように感じます。そうして、「春」の中での男の回想と、私が若い時に「春」を読んだ頃の記憶が同時に重なって甦り、私が過ごした日々への不思議な回想となって現れて来て、記憶の錯綜を知るに至ったのでありました。
今までに中村眞一郎の作品はそれほど読んでおりませんので、今後、初期の作品から評伝まで、思いのままに読んでみたいと考えております。
-
- (Fuさん)
- ・『四季』についての感想他
①中村真一郎の作品の中でも、有名な『四季』は代表作の一つでもあります。冒頭に「春はあけぼの・・・・・・・・清少納言草子」、そして第一章夢の発端は、「それが夢の発端だった――」(改行)突然にKの口から「秋野さんのおじょうさん」という言葉が投げ出された。その名前が冷房のききすぎた夜の部屋の空気のなかで、ブランディーのためにそこだけもやがかかっているように熱していたわたしの脳に、いきなり飛び込んできて明るく弾けた。」と始まっている。そして最後はというと第十章夢の完結、「私はそうした光の氾濫が、徐々に収まって行くのを感じていた。そして、私の前に今まで全く消えていたKの顔が、ゆっくりと姿を取りもどしてくることに気がついた。「これで夢が完結した‐‐‐」(改行)と、私はゆっくりと静かに自分に云いきかせた。」
何故か私は、この四部作の中で、この四季(春)が好きだ。(『夏』が最も読者には読まれているようですが。)この五十歳代の「私」が二十歳代の自分を思い出し、記述しようとしているが、私は記憶喪失に陥っていて、その失った記憶をを友人Kと共に、探しにでかける。探し当てた記憶、回復した記憶が、本当に事実であったという確証はない。事実であったかも知れないし、あるいは想像や夢であったかも知れないという不確実性は作品の最後まで続いていく。中村真一郎の二つの重要な作品の原点は、『源氏物語』と『失われた時を求めて』だと聞いたことがある。この作品にプルーストの作品の影響があったのか?分からないが、少なくとも意識の一部にはあったのではと私は思った。また続く『夏』、『秋』、『冬』の四部作を最初から構想して出発している点を考えると、やはりすごい作家だと改めて思った。
②中村真一郎「人と文学」、特別例会の福永武彦「人と文学」(菅野昭正先生)はとてもいい企画だと思います。作品研究に加え作家の人間や人生研究は、これからも福永研究会として続けていき、研究論文集にも載せていくのがいいと思います。このことにより、作家の実像や人生を知り、より深く作品についても読むことができ、読者は次の時代も読み続けたいという気持ちになってくるのだと確信します。
-
- (Kizさん)
- ・「春」は、夢の発端から夢の完結までの物語となっていて、ここでの"夢"とは、悪夢(戦争)により閉ざされた青春の記憶とされ、老いを意識し始めた私が、意識下に埋もれた記憶の深層を逍遥するという展開になっている。ストーリーが現在と過去を行き来し、想起される記憶も時系列的ではなくて、読みながら過去を再構成し難いもどかしさがあった。しかしながら、そういったところが記憶の本質なのかなと感じて興味深かった。
・"それまで女性経験のない私にとって、女性は夢の対象だった。"という文章からも、"夢"とは、本作に続く「夏」、「秋」、「冬」で深く探求される女性との交渉をも暗示しているようだ。四季4部作において「春」以降の作品は、より作者自身の私的な"夢"に接近しているという感じがした。
-
- (Kinさん)
- Ⅰ.今回、中村眞一郎の文学作品に触れましたが、まず文体に慣れるのに時間がかかりました。そのため、物語の進行を追うのにも同じく時間がかかりました。おそらく、心理描写が多く挿入されるために物語自体の展開が掴みにくかったのだと思います。だとすれば、なぜ私にとって福永武彦の作品は読みやすいのか考えさせられました。それは文体だけではなく、テーマや全体的な問題なのだろうと思います。そのためには、他の中村作品を読んで、比べないと分かりません。福永をより知るために、中村をもっと知りたいと思いました。
Ⅱ.『僕のマドンナたち』、『戦後文学の回想』などのエッセイや評論を読み、中村眞一郎という人は面白い人だと思ったのが第一印象だったと思います。それは勿論、福永や加藤周一に比べ、ウィットに富んでいるということだけではなく、知識や関心の広さにおいても、こんなに面白い人はなかなかいないと思いました。そして『愛と美と文学』を読んで、彼の生涯を知ると、その知識欲や感性が育まれた背景の一端が分かるような気がしました。多彩なテーマで本を書いているということは、読者が作者に触れる入り口が大きく開かれていることでしょう。中村の文学作品を読み進めるとともに、これからもエッセイや評論に触ることによって、より中村眞一郎という人を知りたいと思います。
-
- (Teさん)
- 福永武彦の盟友という理由から、中村真一郎の作品はだいぶ以前に手にしたことはあるが、その内容は今では全く記憶しておらず、従って当時はあまり好印象ではなかった。今回の「四季」は、福永らと共に二夏を過ごしたという軽井沢の「ベアハウス」を彷彿とさせる背景であったため、当時の彼らをイメージしながら興味深く読み進めることができた。また性の違いはあるものの、私自身、年齢的にはこの初老の男性と近いことで理解または共感できる点もあった。ただ、人物の呼び名を、S、F、Hといった無機質な名にしたことで(まさに中村の意図するところだったらしいが)、登場人物らがイメージしにくく、作品に入りこむことが難しかった。また、これまで中村の作品に馴染めなかったのは、あまり簡潔でない中村の文体によるところが大きいのではないかと、改めて思った。
-
- (Maさん)
- 中村真一郎の名前には親しみを感じていた。福永の盟友であり中村の『戦後文学の回想』が私の文学的出発の伴走の一冊なのだから当然であるが、作品はわずかしか読んでいない。私が読もうとしたころに目についた作品は、多彩な女性遍歴や神経疾患の治療を受け記憶を失った話など、当時の私に面白いものではなかった。長編『死の影の下に』も最後まで読み通したのかどうか忘れてしまった。
一方、作家への敬愛の気持ちは変わらずにあった。社会的にも華やかな作家活動だった。世界的な視野で西欧、中国、日本の古典にも広く深く通じ、かつ論じ、その自在な教養と博識は、百花繚乱の高原に遊ぶように晴れ晴れと心を解放した。
晩年の難しそうな史伝はますます手が出なかったが、評論や日本古典についてのエッセイ、自伝の幾冊かを愛読した。
今回、Miさんの提案で中村の「四季」四部作の第一部「春」を採り上げて読んだのは、私にはとても有益だった。読んでなかった何冊かを読むことになった。仲間と共に読むことで読む意欲もわくものである。作品に対する見方感じ方が、特に女性同士で共感した。
中村氏の小説の中の女性に対する見方は、人間として内面的にも平等の意識に立つ女性観でなく、男性の論理に立つ外面的な女性観だと思う。ある種の幻想、偏見があり、それが作品世界への没入を妨げる。作品の時代性をも感じさせる。荷風に似ている気がする。
晩年の中村氏と親しいお付き合いがあり、中村文学を熟知したMiさんの解説が、その辺の事情を作家への愛情をもって解き明かしてくれた(Mi註:私は、荷風とは中村氏の女性観はまったく別物と考えています。近江先生が第9章で述べる性哲学が中村氏の考えに近いと思います。例会では、その点を充分に説明できませんでした)。
早くに母を亡くし、中学生で父を失った生い立ち、その父は先進的英国的な紳士であり実業家、貴族的エピキュリアン,旧い言葉でいえばトンでる人だったようだ。そして、普通の家庭生活はなかった。
私は思わずある言葉が閃いたのだが、優秀な頭脳と並々ならぬ感受性の少年が「発達障害」にならない方が不思議なくらいだ。最近は「発達」に「障害のない者」などあるのだろうか、とさえ思う今日この頃だが。
多くを読まずにこういうことを書くのは面映いが、作家中村真一郎は、世界文学の視野に立って、自らの作品で比較文学的先駆を実現しようとしたのではないだろうか。私には日本の文学者の巨人の一人に思われる。
視力の低下で私はもう多くを読む事はできないが、中村真一郎が正しく再評価されるのを願っている。
-
- (Miさん)
- Ⅰ.『四季』について
「青春の理想と壮年の行動の期間が終り、自分の一生に決着をつける時期に入った」「この第三の時期は、あるいは人の生涯の最高の収穫期なのである」(第2章)という自覚を持って、30年以前、カタストロフィー直前にふた夏を過した高原別荘へ友人Kと脚を運ぶ「私」。「秋野さんのお嬢さん」という言葉に喚起された桜色の靄が、その地の匂いとともに、具体的情景を背景に、友人たち、女性たちへの記憶へと誘い、遠く過ぎ去った青春の日々を生々しく蘇えらせていく。作家である50歳の「私」は、そこに新しい意味を見出すことにより現在の生を照らし返し、新たな創作欲を掻きたてられる。
毎年、夏になると『四季』(春の部)を読み返す一時期がありました。中村眞一郎さんがお亡くなりになって数年間だったでしょう。今、その主人公と同年代となって改めて読み返してみると、実にひと言ひと言が身体に沁み込み、味わい深い小説です。高原を彷徨い歩く「私」に重なるように、著者と一緒に歩き廻った軽井沢・追分のあちらこちらの風景――雲場の池、犀星別荘の庭、本通り裏の脇道、音楽会の会場、そして色後庵別荘など――の中に70代の中村さんの面影が髣髴とし、語りかけてきます。今では20年の昔になった、それらの個人的経験が、今、この『四季』を読むことにより一つの体験へと昇華されていく快楽。
小説の現在(1970年代)、それは今(2014年)から40年以前、中学生だった頃の記憶を誘い出し、その頃は写真でしか知らなかった50代の中村さんの(幻想の)姿を呼び覚まし、その幻想の姿が、それから20年後のよく見知った70代の中村さんの面影へと徐々に変貌していき、そしてその傍らでは30代だった私が何やら語り合っている――様々な記憶と幻想とが絡まり合い、溶け合い、融合していく“奇妙な感覚”――。
この記憶の融合が、年齢を重ねるということなのかもしれません。今までより、著者にずっと近く寄り添って読み進めることができたので、以前には退屈に感じた第2章「夜の思想」の記述もすんなりと納得でき、第7章「夢の暈」の持つ構成上の意義にも気が付きました。何より、(四部作を通して)西欧の文学と同時に、むしろ日本文学の伝統が、わけても王朝文学の伝統としての「宿世」の観念が、小説全体をすっぽりと覆っていることを改めて認識しました。
Ⅱ.中村眞一郎について
偶然を必然(縁 えにし)と捉える中村さんの人生態度は、幼児に母を、中学生の時に父を亡くした氏が、人生の様々な局面で立ち向わねばならなかった難局を切り開くためのひとつの智慧だったのでしょう。人間に関ることはすべて、ひとつひとつ単独で在るのではなく、人類文化という大河の流れの中に浸っているという意識が、氏の魂を平安へと導いたのでしょう。守られる場所のない孤独な青年期(意識の問題ではなく、実際に「家庭」を持たなかった)を送った氏にとっては、魂の平安への希求は切実なものでした。そこからおのずと、文学・芸術への烈しい欲求も、そして高貴な血をひく女性への尽きることのない興味も―知的な面だけでなく、その肉体そのものへの関心も―生まれてきます。それは、長い人類文化の「体現者」、文化の「現実態」への関心と言えるでしょう。
【当日配付資料】
① 中村眞一郎自筆はがきの複写(1941.9 帝國大学編集部 長谷川泉宛)と翻刻+註釈。
小説『四季』に描かれる、カタストロフィー以前の高原別荘から投函された珍しい葉書。
ベアハウスの住所が判明する。翻刻文を会員限定公開。A3 1枚。
② 上記の参考資料として、A.『火の山の物語 わが回想の軽井沢』(筑摩書房 1988.11)より
「35ベアハウスの由来」の複写、B.はがきで言及されているボードレール詩篇「秋の歌」の福永武彦訳の複写を配付。
また、この9月下旬刊行予定の『福永武彦とその時代』(渡邊一民著 みすず書房)の紹介文。A3・1枚。
③ 11月24日開催の「文学フリマ」の日時・内容の御案内。A4・1枚。
①・②:Mi、③:Ki
【回覧資料】
① 中村眞一郎自筆色紙 「年の瀬やまつげにとまる街の塵」 毛筆1枚
② 中村眞一郎自筆色紙 「栗焼くや美濃と近江の国さかひ」 毛筆1枚
③ 中村眞一郎自筆草稿 「恍惚」ペン書き 一部分
④ 上記、複写配付の中村眞一郎自筆はがきの実物。
⑤ 中村眞一郎、生写真。25枚ほど。福永武彦、加藤周一、堀多恵子、水上勉などと。
⑥ 雑誌「山の樹」第13号(終刊号)、復刻でなくオリジナル。
⑦ ネルヴァル著/中村眞一郎訳『火の娘』(1941.8)の山崎剛太郎宛ペン署名本。
⑧ 『ジイド日記 Ⅲ』(小沢書店 新庄嘉彰訳)。日記元版が『四季』で言及される。
⑨ 『小説構想の試み』(書肆風の薔薇 1982)識語入。
⑩ 『死の影の下に』(講談社文芸文庫 1995)署名・落款入。
⑪ 萩原朔太郎『蝶を夢む』(新潮社 1923)
『四季』で女性の肌を魚に例えている一文との類推で、朔太郎の詩篇「その襟足は魚である」を参照した。
①~③:A、④~⑪:Mi
 第147回例会 第147回例会
以下の内容で開催されました。
【日時】 2014年7月27日(日) 13:00~17:00
【場所】 川崎市平和館 第2会議室 参加者:13名(学生:2名 内1名は初参加)
【内容】
1. 小品を読む(第2回)「鴉のいる風景」、「夕焼雲」を採り上げて検討しました。
(1)「鴉のいる風景」についての意見・感想
- 寂しい作品だと思いました。舞台が北海道であり、主人公が詩人であるという二つの点から『夢の輪』の志波英太郎を思い出しました。(Oさん)
- 福永武彦には、『風土』のような南方性の小説と、『死の島』のような北方性の小説がある。「鴉のいる風景」や「夕焼雲」は後者に属する。昼の短い北方の地域では、あるいは、昼の終わりを告げる夕焼けに色々な気持ちをもつのかもしれない。(Kuさん)
- 暗澹とした絵画を思わせるような風景の描写。他の小品3篇とは異なる暗い詩的な作品、ポーの「鴉」(福永訳)を連想します。明るさや希望がなく感じられるのは、体調が良くない時期に書かれたためなのでしょうか。「藝術の慰め」やベックリーンの絵にも、この作品に関係するような絵画は見当たりませんでした。ただ北海道では冬に鴉が群れる荒涼としたこのような景色が見られるようです(加山又造「白い道」)。配布資料から再出になるまでに大幅な改稿がなされたことが解りました。確かに暗い風景を想像しますが、読み返すと暗い感覚は次第に減って情景が浮かび上がります。(Naさん)
- 読んでみると両作品の象徴的な言葉が気になりました。まず「鴉のいる風景」で鴉という象徴からエドガー・アラン・ポーの「The
Raven」の詩を想起し、死もしくは死の世界(冥府とでも言えるのでしょうか)へと繋がる象徴なのかと思いました。(Kinさん)
- この作品と「夕焼雲」で、自身を「詩人」と呼んでいる。すでに単行本の「塔」を前年出版し、療養所では「風土」を書き進めていた福永だが、この時点では小説家よりも詩人であるという自覚がまだ強かったのかと思う。また、Kinさんも触れていたが、福永にとって"鴉"は、自身も翻訳したポーの詩「鴉」(『象牙集』に収録)がいつも念頭にあったと思う。この詩では鴉は冥界の岸から飛来した不吉な鳥とされているが、「鴉のいる風景」においても同様に不吉なものを象徴していると思う。(Kizさん)
- 鴉(カラス)は、印象として死、悪魔の使い、不幸、不気味、暗黒等が上げられる。これはカラスが真っ黒で口ばしが大きく死者の肉を食べる等の習性から来ることが多い。しかし例外もあります。今年4月に「フィンランドとバルト三国」に旅行したとき見たカラスは黒と白の2色のかわいらしいカラスでした。ずいぶん前にNHKの番組で『カラスは白い』のなかで、ある村のカラスは全部白いカラスだった。これは突然変異を受け継いだもので、確かフィンランドの村だったと記憶している。(Fuさん)
- 「鴉のいる風景」と「夕焼雲」に登場する詩人を、私は福永だと思って読んだ。「鴉のいる風景」は「人間嫌い」の詩人を象徴するように、作品全体に寒々とした、全てを拒絶するような空気が漂っている。鴉の群は死神を連想させ、太陽の描写は無機的、夕焼けの描写は重苦しい。詩人と周囲のものとの「距離」が「人間嫌い」を表現しているように思えた。(I
さん)
(2)「夕焼雲」についての意見・感想
- 四人の共通の病を病んだ若者たちが夕焼けの空を共に眺めて、そうして各々の考えを語るというこの掌編から、僕は野間宏の『暗い絵』を思い出しました。暗い絵は四人の若者に「ただ苦しみという点において、互いに親しい交わり合い」があり、彼らは「その絵(題名にもなっているブリューゲルの絵)に共通に打たれ」ていて、その友情の交歓を描いたものだから、まずその点で印象が重なります。また、夕焼雲の最後にその四人のうちの数名の死が語られるのと同じように、暗い絵でも四人のうち三人の死が語られます。つまり、共通の苦しみを抱え、親しい交わりのあった若者たちの魂の交流の一場面とそれへの追憶とを描いた作品であるという点で、この二作は共通しているよう思えるのです。福永さんと野間宏との作品に似たような青春時代への回想が描かれているというのは、二人が第一次戦後派作家であり(この括りはあまり良いとはいえないかも知れませんが、二人とも同じ時代に活躍した作家ではあります)、ということは、二人とも戦争によって多くの友人を喪った者であり、そういう理由から共通のものを持っていたからでしょうか。(Oさん)
- 雄大な北の大地の荘重な日没の風景描写は美しい。詩人の述懐が作者の思いとして読んでいましたが、やはり4人の若い男の発言の総和が福永の夕焼けについての心象風景なのだと思います。夕焼けは終末の風景を暗示しますが、生への希望としても描かれています。(Naさん)
- 討論でも話題になっていたように、夕暮れは福永武彦の小説世界では多く登場する情景(ここでも小説「冥府」を想起しました)であり、昼から夜へと向かう間・中間であるのかと思います。思えば両作品とも作中で夕暮れから夜へと向かう様子が描写されていることも象徴的で、これらは個別に議論してもよいキーワード/テーマであると改めて思いました。また、舞台となる北海道という土地での、福永自身の体験が両作品全体から〈鴉〉や〈夕暮れ〉という象徴に至るまで通底しているのではないか、ということも考えたいです。(Kinさん)
- 夕焼けについての各人の感想が述べられているが、すべて福永自身が夕焼けに抱く想いを作中の人物に語らせたのだと感じた。①詩人:ニルヴァーナ、体験する以前の体験と言い、これは「妣の国」を連想させる。 ②気前のいい青年:子供の頃を思い出す(幼年時代)。 ③太った青年:夕焼けの美しさはデカダンス(頽廃)に通じる。 ④無口な学生:もう一度何とか生きたいと思う(福永自身の切実な想いだったろう)。また、詩人が二度とあのような美しい夕焼けを見ることがなかったのは、当時、生へのせっぱつまった烈しい欲望があった福永自身の「末期の眼」が生涯忘れられないほどの美しい夕焼けを観させたのだと思う。夕焼けのモチーフが後年の作品にたびたび登場するのは、ボードレールやマラルメの詩に喚起されたこと以上に、療養所時代に「末期の眼で見た夕焼けの美しさが強く心に残っていたからではないか。(Kizさん)
- 「夕焼雲」の詩人には、「これから生きていこう」という、前向きな姿勢が見てとれる。夕焼けの描写に切ない影がありつつも、重苦しい感じはしない。例会での、「4人の夕焼けの感想」は、全部福永の分身ではないか?という意外な解釈には納得。色々な人の意見をきくのは、面白いと思った。(I
さん)
(3)短篇2作の本文主要異同について(Miさん)
- 「鴉のいる風景」
ガリ版刷雑誌「ロマネスク 第3号」掲載の初出文を翻刻して配付しました。再出文以降とは、大幅に異なる本文です。大きな違いは、①主語が、初出では「僕」から再出以降は「詩人」に変る。
②初出文では、鴉の群を「人の顔」に見立てる描写はどこにもない。
③初出末尾のマタイ伝からの引用語句が、再出以降では省略される点などを指摘できます。改稿以降の本文は、散文詩集『パリの憂愁』(ボードレール)の憐憫と倦怠、そしてポーをさらりと消化した『氷島』(朔太郎)の絶叫と孤独の響きを指摘できるでしょう。
- 「夕焼雲」
残念ながら初出文(「文学新聞」)は未見です。4篇のうち、この小品のみ療養所退院後の執筆です。『小説 風土』(1952.7)、『草の花』(1954.4)を刊行し、「夢みる少年の昼と夜」、「秋の嘆き」、「深淵」を執筆した直後に当ります。この時期に、9年前の体験を新たに小品として纏めたのは、ちょうどマラルメ詩篇「窓」を改訳(初出は「詩學」50.6)する機会があったことが直接的理由でしょう(『世界詩人全集
4』河出書房 55.10に掲載)。つまり、他の3篇に比して、小説家としてより意識的な作品と言えるのではないでしょうか。
2.会誌第10号に関して
年内刊行予定の会誌第10号に関する装幀と内容の確認、さらに販売方法の検討を行った。
3.当日配付資料】
①『新版 象牙集』(1979.3)より訳詩「窓」(マラルメ)、A4表裏1枚/「ノオト」、A4表裏2枚。
②マラルメ「窓」の原詩、A4 1枚。/鈴木信太郎訳「窓」(岩波文庫『マラルメ詩集』)、A4
1枚。
③「鴉のいる風景」/「夕焼雲」、2小品の本文主要異同表。+「窓」福永武彦初訳(「詩學」50.6)、A3表裏2枚。
④初出「鴉のゐる風景」本文全体の翻刻+註釈。A3表裏1枚。「ロマネスク 第3号」掲載の初出文。
⑤福永武彦自筆はがきの複写(1955.6 文学新聞社
三浦徳治宛)と翻刻+註釈。
小品「夕焼雲」の原稿料催促の内容。A3
1枚。
⑥「国文学 解釈と鑑賞 堀辰雄と福永武彦」(1974.2)より「夕焼け」のモチーフに関する一文(柘植光彦)
⑦会誌第10号 表紙案 A4表裏2枚。
資料提供①・②:Ma、③~⑤:Mi、⑥・⑦:Ki
4.回覧資料
ネット上で検索した、三浦徳治宛の小林秀雄はがきの画像複写。配付資料⑤の関連資料。
5.関連資料紹介
① 福永が終生敬愛し続けた作家、石川淳の岩波文化講演会での肉声を8月末まで聴くことができます。
興味深い、貴重な資料です:岩波デジタルアーカイブス
②9月例会で小説『四季』を採り上げる中村真一郎の随筆集を以下に紹介しておきます。
短く読みやすい文を集めた著作ばかりなので、中村文学入門として格好です。評論・読書論は除きます。
- 『私の百章 ―回想と意見―』 桂書房(1969)
- 『氷花の詩』 冬樹社(1971)
- 『聖者と怪物』 冬樹社(1972)(『私の百章』の新編集版)
- 『愛の法廷』 冬樹社(1973)
- 『暗泉夜話』 読売新聞社(1975)
- 『長い回復期』 青娥書房(1976)
- 『記憶の森』 冬樹社(1980)
- 『わが点鬼簿』 新潮社(1982)
- 『艶なる宴』 福武書店(1982)
- 『夢の復権』 福武書店(1985)
- 『不思議な微熱』 筑摩書房(1988)
- 『火の山の物語』 筑摩書房(1988)
- 『緑色の時間のなかで』 筑摩書房(1989)
- 『色後庵漫筆』 白楽(1990)
- 『暗泉閑話』 阿部出版(1991)
- 『小説家の休業』 筑摩書房(1991)
- 『小さな噴水の思い出』 筑摩書房(1993)
- 『随想集 文学的散歩』 筑摩書房(1994)
- 『人生を愛するには』 文藝春秋(1995)
- 『テラスに立つ少年』 筑摩書房(1995)
- 『私の履歴書』 ふらんす堂(1997)
- 『死という未知なもの』 筑摩書房(1998)
ほとんどは、求められるままに様々な媒体に執筆した短い文章を集めたもので、作家中村真一郎の多面性を知るのに好適な著作です。また、中村氏の生い立ち、文学的経歴を具体的に知るには、上記『私の履歴書』の他に『愛と美と文学』(岩波新書 1989年9月刊)が特にお薦めです。
 第146回例会 第146回例会
以下の内容で開催されました。
【日時】 2014年5月25日(日) 13:00~17:00
【場所】 川崎市平和館 第2会議室 参加者:15名(学生:2名)
【内容】 詩人 村次郎についての発表、福永の小品「晩春記」、「旅への誘い」の2篇を採り上げ、今まで同様に様々な側面より討論をしました。
1.発表「村次郎、その詩と人生」(Fuさん)についての意見・感想
- 村次郎の発表、大変興味深く聞きました。お話しいただいた内容は、村次郎についての概括的なものでしたが、戦後すぐに地方で文学活動を行う知識人の一例として興味を覚えました。青森は東北の中でも作家を多く輩出している県ですが、村次郎と同時代同郷の作家、太宰治や石坂洋次郎との交流があったのか、あるいは八戸というと三浦哲郎がいますが、こちらとの関連はあったのかといった具体的な活動内容も知りたかったところです。青森県は比較的に文学作品、作家を顕彰することが盛んな県ですので、村次郎に関しての郷土に根ざした広報活動を今後続けて行けば、深澤さんが気にしていらっしゃった認知度も上がるだろうと思いました。「亡魚の歌」の複製を手に取り見たところ、戦後すぐの出版でなおかつ地方での出版という点で、紙事情も良くない時期によくあれだけの本が刊行されたと驚きました。当時の詳しい刊行状況など知りたく思いました。(Niさん)
- 村次郎について、これまで僕は何の知識も持っていなかった。恥ずかしいことである。僕の恩師・紅野敏郎先生も、村次郎について語ることはなかった。勿論、紅野先生は村次郎について知っていたとは思う。僕はかつて紅野先生に何気なく平木二六(ひらき・じろう)について語ったが、先生はちゃんと知っておられた。今回の発表をお聴きして反芻したのは、真の勉強とは、他人に教えてもらうのではなく、自分の手でつかみとるということであった。深澤さんの御発表は、素晴らしいものであった。(Kuさん)
- Fuさんの発表を聞き、例会中に詩集を拝見し、村次郎への興味が湧いてきました。特に関心があるのは、マチネ同人との関係です。村次郎と福永武彦、中村真一郎などと、どのような接触があったのか、記録があれば参照してみたいです。もちろん詩人としての仕事にも興味があります、手に入れられるのであれば詩集を手に入れて、よく詩を眺めてみたいものです。(Kinさん)
- Fuさんのご発表は、親炙された村次郎の人と作品を、これから世に知らしめていきたいという熱意の籠ったものでした。今回はその第1回ということで、概略的なご紹介をいただきました。一般には、『忘魚の歌』/『風の歌』(1985)の復刻本や『村次郎全詩集』(2011)は入手困難で、その全文業に触れるのも容易ではないとのことですが、次回には詩集の複写なども配付いただけるとのことですので、これから徐々に、具体的に、詩人村次郎の全貌が顕わになることと期待しています。(Miさん)
- 適切な資料紹介により、幻の詩人と言われる所以がよく理解できた。今後、村次郎の代表作を読ませていただき、一層の理解を深めたい。(Kizさん)
- 村次郎のことを多くの人に知ってもらいたいという、Fuさんの熱意が感じられた。ただ、発言に重複が多かったように思われた。その点を整理して発表すれば、適度な長さにスッキリまとまったのでは、と思った。(Iさん)
2.小品「晩春記」、「旅への誘い」についての意見・感想
- 「晩春記」ができたのが昭和24年(1949年)と説明があったが、福永武彦氏の年譜からすると、氏がマチネポエティックの同人原條あき子さんと結婚したのは1944年日本女子大を卒業と同時、長男池澤夏樹氏が生まれたのは、昭和20年7月7日(1945年)、協議離婚したのが昭和25年(1950年)とすると帯広での実生活では、結婚し新婚生活から離婚の前年に書かれたことになる。晩秋に比べ晩春はさらに悲しく寂しいと感じる。秋に比べ季節の春は、桜が咲き新緑になる生命の力を感じる時期に晩春と思うのは、自分がかなり重い病気で来年の春を迎えられない時や人生の挫折や苦悩に見舞われた時だと、私は思った。この作品のタンポポに対する表現に表れている気がする。先日買った「マチネポエティック詩集」(水声社)の「原條あき子」の詩『春の歌』(詩作時期は不明)をご紹介します。(Fuさん)
菫は空に融けて秋凋む日に
音もなく翅をたたんだ白い蝶
光忘れて眠れば窓の外を
低く過ぎる樹のさやぎ塔に死に
春くるかしら いつどこからか また
永遠の夜を展く思い出よ
ぶらんこの少女 花の挿し亨けよ
陽炎にその身揺らせ 望む彼方
ご覧 黄金の青春 硝子の靴の
シンデレラ ほら かなしみの名付け子の
でも 馭者よ 靴鳴らせ 王子待ちながら
今宵 晴れの装ひ 時の響き
おお 天使 索漠と天の風吹き
消えてゆく お前達 愛の扉から
- 小品の2作品については、討議の時間が短かったということもあり、私自身、充分に意見を申し上げられなかったですが、話し合いが進むにつれて、小品4作が福永の北海道体験と深く結びついているということに興味を覚えました。清瀬のサナトリウムの同人誌に掲載されたにも係わらず、北海道体験が中心に語られていることが、この時期の福永にどのような意味があったのという作家論的な興味を持ちました。出来ることなら初出である「ロマネスク」を確認したいところです。(Niさん)
- 「晩春記」について:私は、全てが実際の出来事であるかのように、この作品をごく自然に読んでしまった。「1里半ある町の歯医者に歩いて行くことは、療養中にはできないのでは。」との発言があった。結核に病状安定の時期があるとは言え、体力がなければ歩いて行くのはやはり無理であり、この部はフィクションかも知れないことに気付いた。しかし、このことは興味深いところではあるが、作品自体の中ではさして重要なこととは思われない。大切なことは読者に何らかのイメージを喚起させることであり、その拡がりが大きいほど作品は素晴らしいと言えよう。「僕は幸福」という描写は、福永の作品ではあまり見当たらない表現だそうである。それではなぜ幸福という語が用いられているのだろう。個人的な事情のせいか、戦時中の療養所という世間から隔絶された環境によるのか、想像だけが膨らむ。幸福と言う心情を北国に春の大地の自然と対応させ、何らかの詩的な情緒あるいは情景を描いているようにも思える。私はこの作品を読んで安堵を覚えた。(Naさん)
- 「旅への誘い」について:ボードレールの詩にデュパルクが曲を付けパンゼラが歌う、その歌は当時人気があったそうである。仕事を終えて、この歌を口ずさみながら、ひとり静かな夜道を歩き家に帰る描写は何とも抒情的である。1932年録音のこの歌を実際に聴いてみて、福永が歌っていた情景が浮かんでくるようである。この題はやはり「旅へのいざない」と読みたい。「小品」に関する福永の全集解説が引用され説明がなされ、「四つの古い小品」への理解が容易になった。(Naさん)
- 『晩春記』の中の「幸福」という表現について考えてみました。
沢山は読んでいませんが、他の福永作品では見たことのないこの表現を、不思議な気持ちで受け止めました。気力の衰えていた暗い時期に書かれた作品であるはずなのですが。「僕」は束の間の満たされた気持ちを、平和のなかにいられることを、幸福という言葉で表現したかったのではないかと思います。ささやかな心の充足を、そう表現することで、そうなのだと思いたかったのです。言い切って「幸福」と書けば、そこに、言葉の力が生じますから。 強いて言えば、「幸福だと思いたかった。」ということだと思います。「ロマネスク」という病院の中の文芸誌に書いた訳ですから、闘病中の患者を読み手として意識して、生きることには光があることや、希望をもたせる感じで書いたのかもしれないと思います。(Kaさん)
- 小品に関しては、僕も『旅への誘い』は(タビヘノイザナイ)と読んでいました。
印象ですが小品『旅への誘い』の物語部分は、最後に引用されるボードレール『旅への誘い』へのイントロダクションのように思えます。仮に、物語の内容が福永武彦の体験に基づくものであると素直に読むなら、自身の生活を芸術に近づけようとする福永の試みなのかもしれない。と、そんなことを思いました。それ以外はまだ意見がまとまりません。(Kinさん)
- わざわざ「小品」と名付けた掌篇2作。それが、小説や随筆と異なる点は『普及版 堀辰雄全集第6巻』(1958)の月報に詳しく論じられていますが(のち、『意中の文士たち 下』人文書院
1973に所収)、その出来具合が異なるのですから、自ずから「読みの勘所」も違うでしょう。1点のみ記します。「僕がなぜ町に行きたく思ったのか、その理由は此所に書く必要はない」(「晩春記」)、「三年の間に色々のことがあったが、それを此所に書く必要はない」(「旅への誘い」)という点、つまり「意識的に書かなかった」こと、この小品の世界から意識的に排除したことがあり、それはもちろん、妻澄子と息子夏樹のことが主でしょうが、それを「書く必要はない」とわざわざ記している点に興味を惹かれます。随筆ならば、連想のままに書き記したでしょう(年譜的事実では、「晩春記」の“僕”の退院日に息子が生まれますから―というより、息子が生まれたから退院したのでしょう―妻は身重です)が、それらの事実を一切を省いています。そこに福永の作家としての靭い意志を感じます。払った犠牲が大きければ大きいほど、或は悦びが大きければそれだけ、通常それを書きたくなるものでしょうが、一見何気なく書かれたようなこの「小品」に於て、福永は日常を切り捨て、自らの作品世界を、―孤独・静謐な世界を―意識的に構築しています。2小品の「味わい」(それは亦、小説とも異なった虚構の少ない、よりintimeな文体による)が、厳しい選択の上に成り立っていることに、心を打たれます。(Miさん)
- 「晩春記」:タンポポの綿毛に死者の魂を思い重ねるところに、死を身近に感じている福永の心象があらわされていると思う。春ののどかな情景描写、幸福感の表明は、発表媒体が療養所内の同人誌であったことも関係しているのだろう。 「旅への誘い」:通勤の列車内で感じた「旅への誘い」のようなもの(2回)と、ボードレールの同名の詩と、その詩にデュパルクが曲を付けたレコードが関連しつつ、3年後の病床でそれらを改めて思い起こし、「旅への誘い」の気分についてのある認識を得るという緻密な構成になっている点がいかにも福永らしく、完成度が高い小品であると思う。(Kizさん)
- 私は「僕」を「福永」だと思って読んでいた。だから、福永が感じている気分や空気を作品にしたものだと解釈していた。療養所での体験や、自分の将来への不安や展望を語った作品と思って読んでいた。(Iさん)
【当日配付資料】
- 「幻の詩人村次郎、その詩と人生」(「中村真一郎手帖第8号」)・「中村真一郎と村次郎と芥川比呂志」(「中村真一郎手帖第9号」)・「村先生の形見」(「朔」第177号)、各A4片面3~4枚。他に、Fuさんの村次郎への篤い想いを記した熊谷拓治氏の一文、A4・1枚。
- 「晩春記」/「旅への誘い」、2小品の本文主要異同表。各A3表裏1~2枚。
- 福永武彦自筆手帖より複写。 ァ1945年、帯広療養所の入院日付等(200%拡大)。ィ 1944年、「獨身者」第1章の構想メモ(原寸)+翻刻。
- 普及版『堀辰雄全集第6巻』(新潮社 1958年)の月報複写(「小品」に関する福永の評論)。ボードレール「旅への誘い」原詩と福永訳(新版『象牙集』より)。A3表裏1枚。
(1:Fuさん、2~4:Miさん提供)
【回覧資料】(Miさん)
- 村次郎詩集『忘魚の歌』復刻本(村次郎詩集刊行会 1985.4)
挟み込みの小冊子に「原本は石橋正一郎氏(村次郎氏の小学生時代の恩師)の名人芸ともいえる謄写刻字になるものであるが、残念なことに不明瞭なところが多いのでそのままの復刻とはせずに活字に換えることにした」とあります(「復刻版を多くの人に」中 寒二)。
【関連資料紹介】(Miさん)
『マチネ・ポエティク詩集』が復刊されました(水声社 2014.5.20 定価4000円+税)。
- 編集ノートによると、「本文に関しては、真善美社版にできるかぎり忠実に従うことを旨とした」とのことです。
巻末に、安藤元雄「『マチネ・ポエティク詩集』について」、大岡信「押韻定型詩をめぐって」の2篇の解説が付きますが、前者は思潮社版『マチネ・ポエティク詩集』(1981)の、後者は思潮社版『中村真一郎詩集』(現代詩文庫 1989)の再録です。せっかくの復刊なのですから、新たな解説が欲しかったところです。
肝心の詩篇本文に関してひと言のみ。真善美社元版に拠らず、思潮社版に拠るべきでした。理由は、画像を御覧ください。上は今回の水声社版、下が思潮社版です。
定型詩を、みた眼でパッと捉えるには、思潮社版に軍配が上がること、それこそ一目瞭然でしょう(全篇同様)。詩篇は眼でも味わうものです。水声社版は、安定感・心地よさに欠けます。これがもし自由詩だった場合、引用の際の行空きにも迷います。福永が生前に刊行した各種の『福永武彦詩集』(麦書房)は、当然、福永の形式感覚が行き渡っていますので、そのような点に配慮をした紙面になっています。
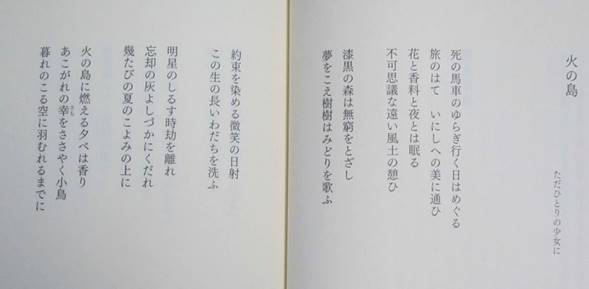
新刊 水声社版より「火の島」
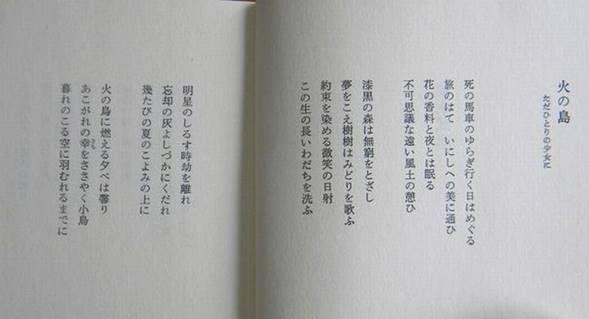
思潮社版より「火の島」
|
HOME|入会案内|例会報告 |会誌紹介|電子全集紹介 | 関連情報 | 著訳書目録|著作データ | 参考文献|リンク集|玩草亭日和(ブログ)|掲示板(会員限定)
|